|
乽杽傕傟偨埨擹捗乿傪扵偡偨傔偵
丂拞悽偵塰偊偨埨擹捗偺柀偲偼丄偳偺抧堟偵偁傝丄偳傫側挰偱偁偭偨偺偐丅偦偺夝柧偵偼丄屆暥彂椶偺帒椏偑彮側偄偨傔丄抧壓偵柊傞偱偁傠偆抧幙傗杽憼帒椏側偳偑丄偦偺桳椡側庤妡偐傝偱偁傞偙偲偼丄娫堘偄側偄丅乽杽傕傟偨埨擹捗乿傪扵偡偙偲偑丄杮峞偺栚揑偱偁傞丅
埨擹捗偼丄埨擹愳丒娾揷愳壨岥嬤偔偺奀娸廃曈偺壂愊掅抧偵敪払偟偨柀挰偱偁傞偑丄偲偔偵亀捗巗巎亁偵傛傟偽丄尰嵼偺娾揷愳塃娸偺捗嫽桍嶳晅嬤偑桳椡偲峫偊傜傟偰偒偨乮攡尨丒惣揷丄1954乯丅偟偐偟側偑傜丄偄偮偺帪戙偐傜柀偺婡擻傪傕偮挰乮廤棊乯偑敪揥偟宍惉偟偰偄偭偨偐丄偄傑偩柧妋偱偼側偄丅傑偨埨擹愳拞壓棳堟偺擺強堚愓側偳偺栱惗堚愓孮偺懚嵼傗丄偲偔偵嬤擭偺埨擹挰戝忛堚愓偐傜偺崗彂搚婍乮俀悽婭拞崰丄栱惗帪戙屻婜乯偺敪尒偼丄偦偺帪戙傑偱埨擹捗偺懚嵼偑熻傞壜擻惈傪埫帵偝偣傞傕偺偱偁傞丅
彮側偔偲傕屆戙偵傑偱扝傟傞偲峫偊傜傟傞埨擹捗偺柀挰偼丄柧墳俈擭乮侾係俋俉乯8寧25擔乮怴楋偵偡傞偲9寧20擔乯偺搶奀壂傪恔尮偲偡傞戝抧恔乮柧墳抧恔乯偵傛偭偰丄偦偺挰偺婡擻偑夡柵揑側懪寕傪庴偗偨偙偲偑丄楌巎揑側帠幚偲偟偰抦傜傟偰偄傞乮堫杮丄侾俋俉俋乯丅偦偟偰丄拞悽偺埨擹捗偺條巕偵偮偄偰偼丄暯惉俉擭偵幚巤偝傟偨埨擹捗桍嶳堚愓偺敪孈惉壥乮埳摗丄1997丄埳摗傎偐丄侾俋俋俉乯傪宊婡偲偟偰丄怴偟偄峫屆妛揑帒椏偑壛傢傝丄偦偺堦晹偑柧傜偐偵偝傟傞偲偲傕偵丄偦偺夝柧偵岦偗偰偺娭怱偑廤傑傞傛偆偵側偭偨丅偟偐偟側偑傜丄偙偺俆侽侽擭慜偺戝嵭奞傗帠曄偵傛偭偰丄埨擹捗偺挰暲傒傗柀側偳偼偳偺傛偆偵曄壔偟偨偺偐丄偦偺幚懺偵偮偄偰偼丄偄傑偩晄柧側偙偲偑傜偑悢懡偔丄撲偵枮偪偰偄傞乮埳摗丄侾俋俋俉丄捗偺儖乕僣傪扵傞夛丄侾俋俋俉乯丅
偲偔偵丄戝抧恔偵傛傞嵭奞慜偺埨擹捗偺柀傗挰偺埵抲傗婯柾側偳偼丄枹偩妋掕偝傟偰偄側偄偟丄偦偺斖埻傕柧傜偐偱側偄丅偦偺偨傔丄懡偔偺悇榑偺恾側偳偑昤偐傟偰偒偨乮椺偊偽巐曽丄1912乯丅偝傜偵丄偙偺戝恔嵭偵傛傞柀徚幐偺庡側尨場偵偮偄偰傕丄亀捗巗巎亁戞侾姫偵傛傞抧恔娮杤偵傛傞傕偺偐乮堥晹丄1984乯丄偁傞偄偼戝捗攇偵傛傞傕偺乮栚嶈丄侾俋俉俋乯偐丄枹夝柧側偲偙傠偱傕偁傞丅
杮尋媶偼丄埨擹捗偺柀傗挰偺埵抲傗婯柾丄婡擻側偳傪夝柧偟丄柧墳抧恔傪慜屻偺埨擹捗偺娐嫬暅尦傪偡傞栚揑偱丄壂愊掅抧偺旝抧宍偺摿挜偐傜丄拞悽偺柀埵抲偺壜擻惈傪偝偖傝丄偝傜偵僕僆僗儔僀僒乕偵傛傞昞憌抧幙挷嵏傪幚巤偟偰丄偦偺扵嵏傪帋傒偨傕偺偱偁傞丅
偙偺挷嵏偼丄乽捗偺儖乕僣傪扵傞夛乿偑拞怱偲側傝丄僕僆僗儔僀僒乕偺奐敪幰偱傕偁傞峀搰戝妛抧棟妛嫵幒丒拞揷 崅嫵庼僌儖乕僾丄捗巗暥壔壽丄捗巗杽憼暥壔嵿僙儞僞乕偺嫤椡傪摼偰丄暯惉10擭搙乽埨擹捗暔岅帠嬈乿偺堦娐偲偟偰丄柧墳抧恔偐傜500擭栚偵偁偨傞1998擭偵幚巤偟偨傕偺偱偁傞丅偙偺曬崘偼1998擭挷嵏偺梊嶡揑側寢壥偱偁傝丄抧幙帒椏偺徻嵶側帋椏暘愅丄擭戙應掕偺寢壥側偳傪傆傑偊偰偺憤崌揑側惉壥曬崘偼丄崱屻偺暘愅尋媶寢壥側偳傕摜傑偊偰丄屻擔偵婜偟偨偄丅
埨擹捗偺柀偺埵抲傪偝偑偡偵偟偰傕丄奀娸嬤偔偺壂愊掅抧偱偁傝丄奀敳乮昗崅乯侽倣晅嬤偐偦傟埲壓偺抧憌傪傕偲偵専摙偡傞昁梫偑惗傑傟傞丅偦偺抧憌偼抧壓悈偱朞榓偝傟偰偄傞偺偑捠忢偱偁傞偐傜丄峫屆妛揑側敪孈側偳偼晄壜擻偱偁傞丅廬棃偼丄偦偺偨傔抧幙儃乕儕儞僌偺僐傾帋椏側偳偐傜丄偦偺暘愅偑側偝傟偰偒偨偑丄偦偺帋椏偺暆偑彫偝偔抧憌偺摿挜偑懆偊偢傜偄偨傔丄柀偺摿挜傪帵偡傛偆側憌憡傗丄捗攇憌側偳傪専抦偡傞偙偲偼崲擄偱偁偭偨乮惣拠傎偐丄侾俋俋俇乯丅
偦偺偨傔丄嬤擭妶抐憌挷嵏側偳偵偁傜偨偵帋嶌偝傟偨抧憌敳偒庢傝憰抲丒僕僆僗儔僀僒乕傪棙梡偟偰丄偦偺惢嶌幰偱傕偁傞拞揷 崅嫵庼偺尰抧嫤椡丄婍嵽側偳偺庁梡偺傕偲偱丄挷嵏傪幚巤偡傞偙偲傪帋傒偨丅僕僆僗儔僀僒乕偺憰抲傗偦偺挷嵏朄偼偠傔丄偦偺桳岠惈丒栤戣揰側偳偼丄拞揷丒搰嶈乮侾俋俋俈乯偵徻偟偄偺偱徣棯偡傞偑丄偲偔偵崱夞梡偄偨憰抲偵偮偄偰偼丄峀搰戝妛強桳偺夵椙宆僒儞僾儔乕3庬傪梡偄偨丅僒儞僾儔乕偺峔憿偼丄暆俁俆們倣倃挿偝俀倣乮幨恀侾乯丄暆俁俆們倣倃挿偝係倣丄暆侾倣倃挿偝侾丏俆倣乮幨恀俀乯偺3庬偱丄岤偝偼偄偢傟傕5乣侾侽們倣偱偁傞丅偦偺嬶懱揑側憖嶌曽朄偵偮偄偰傕丄杮挷嵏偵嶲壛偟偨崅揷乮侾俋俋俋乯偵徻偟偄婰嵹偑偁傞丅
杮挷嵏偱偼丄搒巗巗奨抧偱偺壂愊掅抧偺抧幙挷嵏丄偲偔偵柀偺埵抲専徹傗丄捗攇憌偺専弌偺偨傔偵丄偙偺憰抲傪杮奿揑偵巊梡偟偨嵟弶偺婇偰偱偁傞丅 偙偺挷嵏偱偼丄僕僆僗儔僀僒乕偺帋孈応強偺慖掕丄岎徛側偳偑丄幚巤埲慜偺嵟傕廳梫側億僀儞僩偱偁傝丄挷嵏抧揰偺搚抧採嫙幰傗偦偺廃曈廧柉偺嫤椡偑偁偭偰丄偼偠傔偰壜擻偲側傞丅
傕偪傠傫丄埨擹捗偺埵抲傪悇掕偡傞偨傔偵偼丄奺庬偺嬻拞幨恀椶丄媽抧宍恾丄婛惉偺抧宍暘椶恾丄尰抧挷嵏側偳偐傜丄旝崅抧傗掅幖抧側偳偺抧宍暘椶恾傪嶲峫偟側偑傜丄挷嵏抧揰偺慖掕傪専摙偟偨丅偦偙偐傜梊憐偝傟傞柀側偳偵娭學偡傞抧揰偱丄僕僆僗儔僀僒乕挷嵏偑壜擻側僗儁乕僗偑妋曐偱偒傞搚抧扵偟傪峴偭偨丅
崱夞偼丄挷嵏傪棟夝偟嫤椡傪摼傞偨傔偵丄乽捗偺儖乕僣傪扵傞夛乿偱偼丄97擭偐傜尋媶夛丒曌嫮夛傪夛堳傗巗柉岦偗偵奐嵜偟偰偒偨乮亀埨擹捗峘尋媶亁丄侾俋俋俉嶲徠乯丅偦傟偲暯峴偟偰丄帠柋嬊儊儞僶乕偵傛傞帋孈抧偺尰抧扵嵏丄搚抧岎徛傗挷嵏弨旛丒幚巤丄偦傟偵捗巗丒埨擹挰丒婐栰挰崌摨偺乽埨擹捗暔岅帠嬈乿帠柋嬊偺惛椡揑側庢傝慻傒傗妶摦側偟偵偼丄抁婜娫偱杮挷嵏傪娧揙偡傞偙偲偼晄壜擻偱偁偭偨丅
搚抧慖掕偱偼丄埨擹捗桍嶳堚愓傪拞怱偲偟偨廃曈幖抧晹側偳傪岓曗抧偲偟偰丄偲偔偵夛堳偐傜偺怽偟弌傗帠柋嬊偵傛傞岎徛偺寢壥偐傜丄恾 侾偵帵偡傛偆偵丄
乮侾乯崱捗丄乮俀乯攏抮丄乮俁乯寢忛恄幮丄偱幚巤偟偨丅傑偨丄埨擹捗暔岅帠嬈偵堦偮偲偟偰丄98擭7寧20擔偵偼丄堢惗寬峃岞墍乮媽捗抧曽婥徾戜偱丄埨擹捗桍嶳堚愓偺搶椬傝乯偵偰丄巗柉岦偗偵偙偺挷嵏偺帋孈幚墘偲偲傕偵愢柧夛傪幚巤偟偨丅
傑偨丄杮挷嵏偵嶲壛嫤椡偟偰偒偨峀搰戝妛戝妛堾惗偺崅揷孿懢偵傛傞廋巑榑暥尋媶偱偼丄偦偺屻俋寧埲崀偵巗撪偺奀昹岞墍丄屼揳応丄奀娸挰偲丄導撪偺悢売強偱僕僆僗儔僀僒乕挷嵏傪幚巤偟偨丅偙偙偱偼丄偦偺寢壥偺堦晹偱丄偲偔偵捗攇偵傛傞奾棎憌乮捗攇憌乯偑専弌偝傟偨乮係乯奀娸挰偺帒椏傪丄斾妑専摙偺偨傔偵庢傝忋偘傞丅偦偺抧憌帒椏偺婰嵹側偳偵偮偄偰偼丄偦偺尋媶榑暥傗恾昞側偳傪嶲峫丄堷梡偝偣偰偄偨偩偄偨乮崅揷丄1999乯丅
昞憌抧幙僒儞僾儖偲偦偺摿挜
乮侾乯 崱捗
尰娾揷愳壨岥偺塃娸乮撿懁乯偐傜栺750倣丄垻憜塝偺尰奀昹丄昹掔晹偲桍嶳偺旝崅抧乮媽嵒廈乯偵嫴傑傟偨掔娫幖抧乮屻攚幖抧乯偱丄尰奀娸掔杊偐傜惣侾俉侽倣偺撪棨晹偵埵抲偡傞丅拞悽埨擹捗偺廤棊堚峔偑敪尒偝傟偨埨擹捗桍嶳堚愓乮恾丂侾乯偺嵒廈偺奀娸懁偵愙偡傞幖抧偱丄偙偺堚愓乮媽捗幚嬈崅峑峑掚愓乯偐傜恀搶偵栺俀侽侽倣偺嫍棧偵偁傞丅
徍榓30擭戙傑偱偼丄堫嶌悈揷偲偟偰棙梡偝傟偰偄偨徏壀巵偺敤抧偱丄昗崅栺侾丏俀乣侾丏係倣偱偁傞偲崙搚婎杮恾偐傜悇掕偝傟傞丅98擭3寧31擔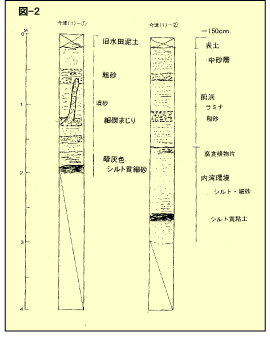 偵丄傑偢梊旛揑偵抧昞偐傜捈愙偵俀倣挿僒儞僾儔乕傪2杮嵦庢偟偨丅昞柺偐傜惙搚憌乮墿妼怓嵒憌乯偑-80乣-90們倣傑偱丄杽愊僑儈-90乣亅150們倣丄悈揷揇憌-180們倣偱偁偭偨偺偱丄婡夿椡偱-侾俆侽們倣傑偱孈嶍偟偨丅偦偙偱偺抧壓悈埵偼丄抧昞柺壓亅110們倣偱偁偭偨丅僒儞僾儖偺嵟忋晹偼丄昗崅傎傏侽倣偵憡摉偡傞偲悇掕偝傟傞丅 偵丄傑偢梊旛揑偵抧昞偐傜捈愙偵俀倣挿僒儞僾儔乕傪2杮嵦庢偟偨丅昞柺偐傜惙搚憌乮墿妼怓嵒憌乯偑-80乣-90們倣傑偱丄杽愊僑儈-90乣亅150們倣丄悈揷揇憌-180們倣偱偁偭偨偺偱丄婡夿椡偱-侾俆侽們倣傑偱孈嶍偟偨丅偦偙偱偺抧壓悈埵偼丄抧昞柺壓亅110們倣偱偁偭偨丅僒儞僾儖偺嵟忋晹偼丄昗崅傎傏侽倣偵憡摉偡傞偲悇掕偝傟傞丅
係倣挿僒儞僾儔乕2杮偺拰忬恾傪丄摨偠孈嶍寠偺拞墰晹傪崱捗乮侾乯亅匑丄偦偺惣栺50乣70們倣偢傜偟偨傕偺傪崱捗乮侾乯亅匒偲偟偰丄恾 俀偵帵偟偨丅
匑 慡懱偱俀侽侽乣俀侾侽們倣偺挿偝偑嵦庢偝傟丄嵟忋晹偐傜亅俁侽們倣傑偱偼丄奾棎偟偨杽愊偝傟偨僑儈傪娷傓昞搚丄媽悈揷揇搚偱偁傞丅偦偺壓亅侾俆侽們倣傑偱丄偍傕偵奃怓側偄偟墿奃怓偺慹嵒丒拞嵒憌傪庡懱偲偡傞偑丄偦偺壓晹偺亅侾俉侽乣亅俀侾侽們倣傑偱丄埫奃怓偺僔儖僩幙偺嵒憌偱丄怓挷偲憌憡偐傜亅侾俆侽乣
亅侾俆俆們倣傪嫬偵偟偰戝偒偔擇暘偝傟傞丅忋晹偺嵒憌偵偼丄亅俇侽乣亅俉侽們倣丄亅侾俁侽乣亅侾係侽們倣丄亅侾俆俆乣亅侾俇俆們倣丄嵶釯傑偠傝墿妼怓側偄偟墿奃怓偺慹嵒晹偑嶰憌擣傔傜傟丄悈暯側儔儈僫傪傕偪塤曣曅偺栚棫偮墿奃怓偺拞嵒憌偵嫴傑傞偺偑摿挜偱偁傞丅 偲偔偵丄偙偺忋擇憌偺慹嵒憌偺娫偵丄挿偝俇侽們倣傎偳暆俉乣侾侽們倣偺墿怓慹嵒偺暚嵒偑丄拞嵒憌傪娧偄偰偄傞偺偑妋擣偱偒傞丅偒傢傔偰摿堎側暚嵒尰徾偑丄傎偽姰慡側宍偱帒椏偲偟偰庢摼偱偒偨偙偲偼丄偍偦傜偔拰忬僒儞僾儖偲偟偰偼偙傟傑偱偵曬崘椺偑抦傜傟偰偄側偄丅偦偺偨傔丄 捗巗暥壔壽偱偼丄偙偺僒儞僾儖忋晹偺暚嵒晹傪拞怱偵丄曐懚梡偵攳偓庢傝抐柺偲偟偰丄揥帵偵傕棙梡偱偒傞傛偆偵偟偰偄傞丅
匒 婎杮揑偵偼丄匑偺摿挜偲戝偒偔曄傢傜側偄偑丄偝傜偵壓晹曽岦偵偼丄匑傛傝傕栺侾俀侽們倣傕偺挿偝傑偱丄慡懱偱栺俁侽侽們倣挿偺僒儞僾儖偑嵦庢偱偒偨丅嵟忋晹偐傜亅俀侽乣亅俁侽們倣偼奾棎晹暘偱偁傝丄偦偺壓晹偼嘆偲摨條偵丄亅侾俈侽乣亅侾俉侽們倣偺忋壓偱丄怓挷傗憌憡偑戝暿偱偒傞丅偦偺嫬奅晹偼丄柧妋側棎傟偨峔憿偼側偔悈暯側憌棟偱嬫暘偝傟丄嵟壓晹偺亅俁侽侽們倣傑偱埫奃怓偺僔儖僩幙嵶嵒傗擲搚幙嵒偐傜庡偵峔惉偡傞丅偲偔偵丄亅侾俉侽乣亅侾俉俆們倣偵偼丄晠怘幙偺憪杮椶傗栘曅椶偲巚傢傟傞傕偺偑丄埫奃怓偺僔儖僩幙嵶嵒偵枾廤偟偰偄傞丅偦偺壓晹偼丄偡傋偰憌棟偑偁傑傝柧敀偱側偄埫奃怓偺僔儖僩幙嵶嵒偱丄塤曣曅偑懡偄偺偑摿挜偱偁傞丅傑偨亅俀俇侽乣亅俀俈侽們倣偵偼擲搚幙崿偠傝僔儖僩偺揇幙晹偑嫴傑傞丅堦曽丄亅侾俉侽們倣傛傝忋晹偼丄匑偲摨條偵丄嵶釯傑偠傝墿妼怓側偄偟墿奃怓偺慹嵒晹偑丄悈暯側儔儈僫傪傕偪塤曣曅偺栚棫偮墿奃怓偺拞嵒憌偵嫴傑傞偑丄偲偔偵亅俆侽乣亅俇侽們倣丄亅侾侾侽乣亅侾俀侽們倣偱偼丄偦偺忋壓偵斾傋丄嵶釯偺傑偠傞慹嵒晹暘偑擇憌妋擣偝傟丄嘆偺忋晹擇憌偵傎傏楢懕偡傞偲懳斾偝傟傞偑丄匑偵傛偆側嶰憌栚偑晄柧偱偁傞丅傑偨丄暚嵒偺峔憿傕懚嵼偟偰偄側偄丅
偙偺擇杮偺僒儞僾儖偐傜偼丄匒偱柧傜偐側傛偆偵丄亅侾俈侽乣亅侾俉侽們倣傪嫬偵偟偰抧憌偺摿挜偑擇暘偝傟丄戝偒偔懲愊娐嫬偑曄壔偟偨偙偲偑擣抦偝傟偨丅忋晹偼丄棻搙傗儔儈僫偐傜丄捈愙偵奀偵柺偟偨奀昹偺娐嫬壓偵偁偭偨偲悇掕偝傟傞丅傑偨丄擇丒嶰憌偺侾侽們倣慜屻偺嵶釯傑偠傝慹嵒晹傪嫴傓偺偼丄壨愳偐傜偺嫙媼偺塭嬁傗崅攇帪偺懲愊傪埫帵偡傞丅堦曽丄壓晹憌偱偼僔儖僩幙嵶嵒傪庡懱偲偟儔儈僫傕晄柧妋側偙偲偐傜丄奀昹晹偲偄偆傛傝撪榩揑側懲愊娐嫬偱丄捈愙奀偐傜攇楺偵偝傜偝傟側偄妰偺傛偆側忬嫷偲峫偊傜傟傞丅偲偔偵偙偺嵟忋晹偵怉暔偺晠怘憌傪廤愊偡傞偙偲偼丄埊尨傪傕偮傛偆側妰屛偺悈曈傕堦晹偵偁偭偨傛偆偱偁傞丅
偙偺忋壓憌偺嫬奅偼丄昗崅偱尰奀柺壓栺亅侾俉侽們倣偱偁傝丄偦偺怺偝慜屻傪傕偮妰屛偑丄奀昹偵曄壔偟偨娐嫬偺曄慗傪暔岅傞丅尰抜奒偱偼丄擭戙應掕偺帒椏偑側偄偺偱丄偙偺曄慗擭戙偑晄柧偱偁傞丅傑偨偙偺嫬奅柺偵偼丄柧椖側怤怘偟偨嵀愓偑妋擣偱偒側偄偱丄偙偺娐嫬偺曄壔偑戝捗攇側偳偵傛傞傕偺偐斲偐偼丄敾掕偱偒側偄丅
匑偺忋晹憌偵偼丄偒傢傔偰捒偟偄暚嵒峔憿偑柧敀偵懆偊傜傟偨丅偙傟偼丄忋晹憌偺懲愊屻偺抧恔偵傛傞壜擻惈偑崅偄偑丄偦偺擭戙偼晄柧偱偁傞丅側偍丄偁傑傝偵僒儞僾儖拞墰偵柧椖側暚嵒峔憿偑摼傜傟偨偺偼丄嬼慠偵偟偰傕偁傑傝偵婏嬾偐摿堎側傕偺偱偁傞丅偦偺偨傔丄偁傞偄偼僒儞僾儖嵦廤帪偺怳摦丄偲偔偵奧傪懪偪崬傓帪側偳偵丄恖岺揑偵嬼慠偵惗惉偟偨暚嵒峔憿偲偺媈栤傕側偄栿偱偼側偄丅崱屻偺専摙壽戣偲偟偨偄丅
乮俀乯 攏抮
埨擹捗桍嶳堚愓偺恀撿偵栺俀侽侽倣偺埵抲偵偁傝丄嵒廈偺娫偺嫹偄掔娫幖抧偵偁傝丄拞搰巵偺媥峩揷偲側偭偰偄傞丅昗崅偼俀丏侽倣傎偳丄攏抮偺帤柤偺捠傝丄偐偭偰偼抮偑偁偭偨偲揱彸偝傟傞偑丄偦偺斖埻偼晄柧偱偁傞丅
98擭3寧31擔偵偼丄暆侾倣倃挿偝侾丏俆倣偺僒儞僾儔乕偱丄梊旛揑側嵦庢傪峴偭偨丅
抧昞偐傜亅侾丏俆倣傑偱偼丄偡傋偰悈揷偺揇憌偲偦傟埲慜偺栘曅丒抾曅側偳傪娷傓杽傔棫偰搚憌偲敾抐偝傟傞傕偺偱偁偭偨丅
丂俈寧侾俋擔偵丄係倣挿偱嵦庢偟偨寢壥偼丄抧昞壓亅俁丏俀倣傑偱偺恾3偵帵偟偨崅揷乮侾俋俋俋乯偵傛傞丅偦偺愢柧偵傛傞偲丄抧昞偐傜亅侾俆們倣傑偱偑昞搚偱丄偦偺壓偐傜亅俇俆們倣傑偱偼丄埫奃怓偺嵶乣拞棻嵒偐傜側傝丄拞悽偛傠偺傕偺偲巚傢傟傞搚婍曅偑崿嵼偡傞丅偦偺娫丄亅俁俆乣亅俁俉們倣偵偼搼懣偺傛偄奃怓嵶棻嵒偑嫴傑傞丅亅俇俆乣俉俆們倣偵偼奃怓嵶棻嵒傪庡懱偲偟丄埫奃怓晠怘幙僔儖僩偑斄揰忬偵崿嵼偟丄亅俉俆乣亅侾侾侾們倣傑偱偵偼拞棻嵒傪娷傓埫奃怓嵶棻嵒偲側傝丄偲偔偵亅侾侽俆乣侾侾侽們倣偵偼柧墿奃怓偺慹棻嵒偑嫴傑傞丅
偦偺壓亅侾侾侾乣侾俆侽們倣傑偱偼丄奃怓乣墿奃怓偺嵶棻嵒偑懲愊偟丄挊偟偔棎偝傟偨峔憿傪傕偭偰偄傞丅亅侾俆侽乣亅俀俁俉們倣偼嵶乣拞棻嵒偐傜側傝丄柧椖側儔儈僫乮梩棟乯峔憿偑擣傔傜傟丄忋晹偱偼悈暯側儔儈僫丄壓晹偱偼孹幬偡傞儔儈僫偲側傞丅偲偔偵亅俀俁俉乣亅俀俇俇們倣偵偼丄僋儘僗儔儈僫乮幬岎梩棟乯偐傜側傞搼懣偺傛偄嵶棻嵒偲側傞丅亅俀俇俇乣亅俁俀侽們倣偼嬒幙側嵶棻嵒偱丄儔儈僫偼擣傔傜傟側偄丅亅俁俀侽乣亅俁俁侽們倣偼奃怓偺嵶棻嵒傪庡懱偵偟偰丄晠怘幙僔儖僩傗栘曅偑崿擖偡傞丅偙傟傛傝壓埵偼丄搼懣偺偁傑傝傛偔側偄拞棻嵒偐傜側傝丄宎侾們倣傎偳偺嵒釯偑崿偠偭偰偄傞丅
恾偵傕帵偡傛偆偵丄亅侾俆侽們倣傪嫬偵偟偰丄偦偺壓晹偼丄偦偺懲愊忬懺偐傜奀昹偺傢偢偐壂崌偄偵埵抲偡傞偺壂昹娐嫬偐傜慜昹乮奀昹乯偵曄傢偭偨偲峫偊傜傟丄奀偑愺偔側傞奀戅夁掱偺娐嫬傪帵偡傕偺偱偁傞丅偦傟偐傜忋晹憌偼丄揇幙偺嵶棻嵒偐傜側傝丄撪榩壔偟偰妰屛傗幖抧乮奀昹傗嵒廈偺旝崅抧偵埻傑傟偨掅幖抧乯偲側傝丄尰嵼偺抧宍偺傛偆側掔娫幖抧偲側偭偨偲悇掕偱偒傞丅忋晹憌偺嵟壓晹偵偼奾棎偝傟偨憌憡乮亅侾侾侾乣亅侾俆侽們倣丄昗崅侽丏俆倣傎偳乯偑偁傝丄偙傟偼捗攇憌偺壜擻惈傕偁傝丄偦傟埲屻偵娐嫬偑戝偒偔奀昹偐傜撪棨壔偟偰幖抧偵曄壔偟偨偙偲傪埫帵偟偰偄傞丅
乮俁乯 寢忛恄幮
挀幵応偺撿搶抂偱丄嵒廈晹偲巚傢傟傞抧揰偱丄昗崅偼栺侾丏俋倣偲晅嬤偺昗崅抣偐傜悇應偝傟傞丅俈寧侾俋擔屵慜拞偵丄惙搚偑岤偄偨傔丄抧昞壓亅侾侾侽們倣傑偱孈嶍偟偰丄係倣挿傪俀杮嵦庢偡傞丅俀杮偼摨偠偲偙傠偱丄傎偲傫偳摨堦偺憌憡偺摿挜傪側偡偺偱丄偦偺偆偪偺堦杮傪丄崅揷乮侾俋俋俋乯偺婰嵹傗愢柧傪嶲峫偵偟偰丄弎傋偰傒偨偄乮恾俁乯丅
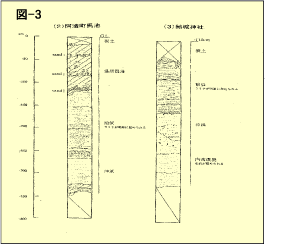
亅係丏係倣傑偱偺僒儞僾儖傪嵦廤偱偒偨偺偱丄幚嵺偺僒儞僾儖偼俁俁侽們倣偺挿偝偱偁傞丅亅侾侾侽乣亅侾俆侽們倣傑偱偼惙搚偱偁傝丄偡側傢偪抧昞壓侾丏俆倣傑偱拞嵒傪庡懱偲偟偨惙搚偱丄抧壓悈柺偑亅侾侽侽們倣傎偳偵擣傔傜傟偨丅亅侾俆侽乣亅侾俉侽們倣傑偱偼丄慹乣拞棻嵒偐傜側傝柧椖側悈暯側儔儈僫偑尒傜傟丄亅侾俈侽們倣晅嬤偵宎侾侽們倣傎偳偺妏釯偑崿擖偟抧憌傕棎傟傕偁傝丄恖岺夵曄傪庴偗偰偄傞壜擻惈偑嫮偄丅亅侾俉侽乣亅俀俇俁們倣偵偼丄柧椖側悈暯儔儈僫傪帵偡丄搼懣偺傛偄嵶棻嵒偐傜側傝丄強乆偵塤曣偺廤愊憌偐偁傞丅側偍丄忋埵偺憌偲偺嫬偼怤怘惈偺傛偆偵巚傢傟傞丅亅俀俇俁乣亅俀俉俆們倣偼丄儔儈僫偺晄慛柧側嬒幙側嵶棻嵒偱丄忋埵偲偺嫬奅偼柧椖側怤怘柺偲側傞丅亅俀俉俆乣亅俁侽侽們倣偼丄晠怘幙偺僔儖僩傪夠忬偵娷傒丄儔儈僫偺晄柧椖側嵶棻嵒偐傜側傞丅亅俁侽侽乣亅係係侽們倣傑偱偼丄埫奃怓偺嵶棻嵒偑傎傏悈暯偵懲愊偟偰偄傞偑丄儔儈僫偼晄慛柧偱偁傝丄惗嵀傗塤曣偺廤愊憌偑強乆偵擣傔傜傟傞丅
亅侾俆侽們倣傑偱惙搚偱丄偦偺嵟壓晹偺昗崅偼栺係侽們倣傎偳偱偁傞丅偦偺壓晹偼亅俀俉俆們倣傑偱偼丄儔儈僫偺摿挜偐傜奀昹乮慜昹乯偺娐嫬壓偵偁偭偨偑丄偦偺亅俁侽侽們倣偼丄僔儖僩傪娷傒壂昹偺忬嫷偲巚傢傟傞偑丄幖抧憌傪姫偒崬傫偱懲愊偟偰偄傞偺偱丄捗攇憌偺壜擻惈傕偁傞丅亅俁侽侽們倣埲壓偺壓晹憌偼柧傜偐側撪榩娐嫬傪帵偟丄彮側偔偲傕尰昗崅偐傜悈怺侾倣埲忋偺妰屛傗幖抧偱偁偭偨偲悇榑偝傟傞丅
乮係乯 奀娸挰
崅揷乮侾俋俋俋乯偼丄忋婰偺挷嵏偺偁偲丄撈帺偱捗巗偺増娸晹偱丄摨條側僕僆僗儔僀僒乕偵傛傞挷嵏傪幚巤偟丄娾揷愳偺嵍娸偺奀娸挰偲屼揳応偐傜丄柧傜偐側捗攇懲愊暔傪敪尒偟偨偙偲傪曬崘偟偨丅偲偔偵柧椖側傕偺偲偟偰丄奀娸挰偱偺俀倣挿僒儞僾儖偺堦晹乮恾係乯偼丄攳偓庢傝張棟偟偰揥帵帒椏偲偟偰捗巗暥壔壽偱曐懚偟偰偄傞丅
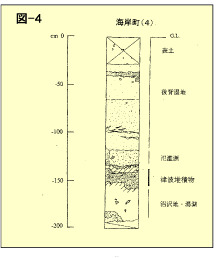
偙偺抧揰偼丄奀娸偐傜俀俆侽倣偺嫍棧偵偁傞悈揷愓偺掅幖抧偱丄昗崅偼傎傏侽倣偱偁傞丅崅揷乮侾俋俋俋乯偺傛傞俶亅侾僒儞僾儖偺憌憡婰嵹傪丄傑偲傔傞偲師偺捠傝偱偁傞丅抧昞偐傜亅俁侽們倣傑偱偼惙搚乮媽峩嶌搚乯丄偦偺壓亅係侽們倣傑偱傑偱偼埫奃怓嵒傑偠傝僔儖僩偱丄悾屗暔曅偺崿擖偐傜恖岺搚憌偲巚傢傟傞丅亅係侽乣亅俇俆們倣偼丄埫奃怓嵒幙僔儖僩偱丄俆們倣憌岤偺柧墿奃怓慹棻嵒偑儗儞僘忬偵嫴傑傝丄傑偨宎侾們倣掱搙偺釯傕崿偠傞丅亅俇俆乣亅侾侽侽們倣偼丄柧奃怓偺僔儖僩幙嵶乣拞棻嵒偐傜側傞丅亅侾侽侽乣亅侾侽俆們倣偼丄埫奃怓晠怘幙僔儖僩幙嵒傪嫴傫偱丄慹棻嵒崿偠傝偺僔儖僩偑亅侾侾俉們倣傑偱懲愊偡傞丅亅侾侾俉乣亅侾俁俆們倣偼奃乣墿奃怓偺慹棻嵒丒嵶釯丄亅侾俁俆乣亅侾係侾們倣偼埫奃怓晠怘幙僔儖僩偐傜側傞丅亅侾係侾乣亅侾俆侽們倣偼搼懣偺傛偄慹乣拞棻嵒偺儔儈僫偐擣傔傜傟傞偑丄壓埵偺奃怓僔儖僩幙擲搚傪嶍傝崬傫偩怤怘柺捈忋偼丄傗傗慹棻偲側傝搼懣偑偁傑傝傛偔側偄丅亅侾俆侽乣亅侾俉俆們倣偼嬒幙側奃怓擲搚偱丄搼懣偺傛偄拞棻嵒偑夠忬偵崿擖偡傞丅亅侾俉俆們倣埲壓偵偼烌乣墿奃怓偺拞丒慹棻嵒偲側傞丅
亅侾俆侽們倣偺怤怘柺傪嫬偵偟偰丄戝偒偔憌憡偑曄壔偡傞偑丄壓埵偺擲搚憌偼丄撪榩娐嫬偵懲愊偟偨傕偺偱丄尰奀娸偵増偆傛偆側昹掔偺攚屻偺妰屛傗掅幖抧偲悇掕偝傟傞丅傑偨偙偺擲搚憌偵崿擖偡傞夠忬偺拞棻嵒偼丄掙惗惗暔偺惗嵀偲峫偊傜傟傞偑丄妋幚側徹嫆偼摼傜傟偰偄側偄丅偙偺柧椖側怤怘柺偲捈忋偺嵒憌偺宍懺偐傜偼丄捗攇偵傛傞媫寖側懲愊曄壔偺壜擻惈偑偁傞丅偦傟傪専摙偡傞偨傔丄俁曽岦偺柺僒儞僾儖傪怴偨偵嵦庢偟偨寢壥丄怤怘偺孈傝崬傒偑俈乣侾侽們倣偺怺偝偱偁傝丄偙偺嵒憌偺帵偡棳岦偼丄撿搶偐傜杒惣曽岦偵岦偐偆傕偺乮尰娾揷愳壨岥偐傜撪棨曽岦偵乯偲妋擣偱偒偨丅傑偨忋埵偺嵒憌偵偼擲搚偑夠忬偵庢傝崬傑傟丄壓埵偺擲搚憌偐傜姫偒忋偘傜傟偨偲悇掕偝傟傞丅偙傟傜偼丄偙傟傑偱偵曬崘偺偁傞捗攇懲愊暔偺峔憿乮Flame structure乯偲傛偔椶帡偟偰偍傝丄捗攇憌偲悇掕偝傟傞乮崅揷丄侾俋俋俋乯丅
捗巗椪奀晹偺暯栰晹偼丄埨擹愳傪拞怱偵塤弌愳丄巙搊栁愳側偳偺壨愳懲愊偵傛傞壂愊掅抧偲奀娸掅抧偐傜宍惉偝傟偰偄傞丅偦偺抧宍揑側摿挜偼丄寶愝徣崙搚抧棟堾乮侾俋俇俋乯丒嶰廳導乮侾俋俋侽乯側偳偺搚抧暘椶挷嵏乽抧宍暘椶恾乿傛傟偽丄奀娸慄偵暯峴偡傞俁乣係楍偺旝崅抧乮嵒廈丄掔廈乯偲偦偺廃埻偺掅幖抧乮掔娫幖抧丒屻攚幖抧乯丄傑偨壨愳偺増偆旝崅抧乮帺慠掔杊乯偲偦傟偵敽偆斆棓尨乮屻攚幖抧乯傕偁傝丄堦斒偵慜幰偑奀娸掅抧丄屻幰偑壨愳乮壂愊乯掅抧偺摿挜偱偁傞丅崱夞偺帋孈挷嵏偼偡傋偰奀娸掅抧偵偁傞掅幖抧偺抧宍偺斖埻偱幚巤偝傟偨丅
椪奀暯栰晹偺抧幙丒抧斦峔惉偵偮偄偰偼丄偦偺昞憌抧憌偼偦偺抧宍偲娭楢偟偰丄忋晹嵒釯憌乮嵟忋晹擲搚憌偲忋晹嵒釯憌乯偲忋晹擲搚憌偲偵嬫暘偝傟偰偄傞乮捗巗丄侾俋俉侽乯丅偟偐偟丄僕僆僗儔僀僒乕挷嵏偺傛偆側徻嵶側憌憡傪嬫暘偟偨傕偺偱側偔丄崱夞偺挷嵏偱偼丄偙偺忋晹嵒釯憌偵憡摉偡傞抧堟偲峫偊傜傟傞丅
偟偑偟側偑傜丄尰嵼偺巗奨抧偺晹暘偼丄僕僆僗儔僀僒乕挷嵏偐傜傕柧敀側傛偆偵丄侾倣傎偳偺惙搚側偳恖岺夵曄偑恑傒丄暯栰晹偺帺慠忬懺偵嬤偄側抧宍抧幙傪惓妋偵攃埇偡傞偺偼丄屆偄抧宍恾側偳傪棙梡偟側偄偲梕堈偱側偄偲偙傠傕彮側偔側偄丅
崱夞偺挷嵏抧揰偼丄拞悽柀傪妋擣偡傞偙偲傪庡栚揑偲偟偰偄傞偺偱丄旝崅抧乮嵒廈乯傪旔偗偰丄掅幖抧偵弌棃傞偩偗尷掕偟偰幚巤偟偨丅偙傟傑偱偺抧宍丒抧幙偺抦尒偲偲傕偵丄崱夞偺挷嵏寢壥傪専摙偡傞偲丄乮侾乯崱捗偼丄嵟傕奀娸傛傝偺掔娫幖抧偱丄徍榓俁侽擭戙傑偱悈揷偱偁偭偨丅帋孈偺寢壥丄杽傔棫偰傜傟偨悈揷憌偼丄昗崅偱亅俁侽們倣傑偱偱丄偦偺壓亅侾丏俉倣傑偱偼丄慡懱偵奀昹乮慜昹乯懲愊暔偵丄堦晹偵壨愳懲愊偺塭嬁傪偆偗偨嵒釯偺廤愊偑偁偭偨偲悇掕偝傟傞丅偦偺壓晹偼昗崅亅俁丏俀倣傑偱偼撪榩娐嫬偺妰屛丄幖尨偺懲愊暔偱偁傝丄悈怺俀倣傎偳偺峘榩晹偱偁偭偨壜擻惈偑峫偊傜傟傞丅
偙偺亅侾丏俉倣傪嫬偵忋壓憌偱丄戝偒側娐嫬曄壔偑偳偺擭戙側偺偐妋掕偱偒側偄偑丄柧墳抧恔埲屻偵拞悽柀偑徚柵偟偨帠幚偲揔崌偡傞傛偆偵巚傢傟傞丅偙偺娐嫬曄壔偼丄撪榩偑奀昹傊偲曄壔偟偨傕偺偱丄奀柺曄壔偑婲偙傜側偄偲偡傟偽丄撪榩偲奜梞傪嫬偟偰宍惉偟偰偄偨掔杊忬偺嵶挿偄嵒廈傗嵒歿偑攋夡偝傟丄徚柵偟偨尰徾傪峫偊傜傟傞丅偲側傟偽丄柧墳抧恔偵傛傞捗攇偱丄撪榩偺慜偺嵒廈乮埨擹徏尨偲悇嶡偝傟傞乯偑徚偝傟偨寢壥偱偼丄側偐傠偆偐丅側偍丄柧妋側撪榩憌傪怤怘傗嶍傝崬傓傛偆側捗攇憌偼丄偙偺抧揰偱偼妋擣偝傟側偄偑丄偙偺嫬奅晹偺捈忋偺憌憡偼捗攇偵傛傞妰側偳偺杽愊偵傛傞懲愊暔偐傕偟傟側偄丅
寢忛恄幮偺乮俁乯抧揰偼丄嵒廈偺忋偵偁傞偑丄昗崅侾丏俋倣偲偦偺惙搚検偺栺侾丏俆倣傪峫偊傞偲丄廃埻偵偁傞悈揷柺偲摨偠偔尰奀昹偵嬤偄丅慜婰偟偨乮侾乯亅嘇僒儞僾儖偲乮俁乯寢忛恄幮偺偦傟傪斾妑偡傞偲丄椉幰偲傕偵忋壓憌偵戝暿偝傟丄壓晹偺撪榩娐嫬偐傜忋晹偵奀昹丒慜昹娐嫬偵曄壔偟偨嫟捠偺摿挜偑擣傔傜傟傞丅昗崅偱亅侾丏侾倣埲壓偑壓晹憌偺撪榩惈偺懲愊暔偱偁傞偐傜丄悈怺侾倣傎偳偺妰屛偑丄杽愊偝傟奀昹偵曄壔偟偨偲悇掕偝傟丄乮侾乯崱捗偲摨偠娐嫬曄壔傪扝偭偨傛偆偱偁傞丅
堦曽丄乮俀乯攏抮偺抧揰偱偼丄掔娫幖抧偵埵抲偡傞偑丄僒儞僾儖偺亅侾俆侽們倣乮昗崅栺侽丏俆倣乯傪嫬偵偟偰丄壓晹憌偺奀昹娐嫬偐傜丄忋晹偵幖抧娐嫬傊偲曄壔偟偰丄慜婰偟偨乮侾乯乮俁乯偺抧揰偲偼丄媡偺娐嫬曄壔偺夁掱傪帵偟偰偄傞丅傑偨丄偙偺忋壓憌偺嫬奅偼丄捗攇偵傛傞奾棎憌偺壜擻惈偑偁傞丅
偙偺傛偆偵丄偙傟傜俁抧揰偲傕丄忋壓憌偺懲愊娐嫬偺曄壔偵偼丄奀柺曄壔偵傛傞尨場偑堦斒偵峫偊傜傟傞偑丄偦偺応崌乮侾乯乮俁乯偼奀柺忋徃丄乮俀乯偼奀柺掅壓偺梫場偲側傞丅偙傟偑摨帪戙偐偼晄柧偱偁傞偑丄傕偟摨帪偺尰徾偱偁傟偽丄捗攇側偳偵傛傞塭嬁偱丄偦偺娐嫬偑戝偒偔曄壔偟偨偲峫偊傞偺偑丄嵟傕柕弬偼側偄傛偆偵巚傢傟傞丅
傑偨奀娸挰偱偺乮係乯僒儞僾儖偐傜偼丄崅揷乮侾俋俋俋乯偵傛傟偽丄柧妋偵捗攇憌偑妋擣偝傟偰偄傞偺偱丄忋婰偺俁抧揰偱偺懲愊娐嫬偺曄壔偵偼丄奀柺曄摦側偳偵傛傞傕偺偱側偔丄捗攇偵傛傞抧宍曄壔偑偦偺懲愊応傪戝偒偔曄偊偨偲悇榑偝傟傞丅
偙偺傛偆偵丄傕偟傕捗攇偵傛傞懲愊娐嫬偺曄壔偑偁偭偨偲偡傟偽丄偄偮崰偺捗攇偵傛傞傕偺偱偁傠偆偐丅埨擹捗乮捗巗廃曈乯傪廝偭偨偲峫偊傜傟傞楌巎捗攇偼丄搶奀丒撿奀壂偺嫄戝抧恔偵敽偆傕偺偱丄塱挿抧恔乮1096乯丄柧墳抧恔乮1498乯丄宑挿抧恔乮1605乯丄曮塱抧恔乮1707乯丄埨惌搶奀抧恔乮1854乯側偳偑抦傜傟偰偄傞乮搉曈丄1985乯丅
捗攇崅偺悇掕偱偼丄柧墳抧恔偑嵟戝偱偁傞偑丄偦偺嵭奞偺忬嫷偵娭偡傞帒椏偑側偄丅偲偔偵宑挿抧恔埲慜偺旐嵭婰榐帒椏偼側偄偑丄曮塱抧恔乮1707乯偺捗巗撪偺旐嵭偼丄壠壆搢夡丒懝彎551屗丄峕屗嫶偑棊偪丄怴揷掔偑寛夡偟丄崅挭偑揷敤偵怤擖偟丄堦晹嵒偱杽杤偟偨丅傑偨掔杊寛夡丂970倣丄掔杊攋懝丂13,260倣丄摏攋懝丂24丄嫶攋懝丂俇丄幬柺曵夡丂28丄壠壆搢夡丂136屗丄壠壆敿夡丂215屗丄嵒擖悈墴揷丂2.2ha丄幀擖揷敤丂397ha丄惢墫梡恉偺棳幐丂3300懇偱偁偭偨丅傑偨埨惌搶奀抧恔乮1854乯偱偼丄杒偼挿搰挰偐傜擇尒傑偱偵傢偨偭偰奀娸掅抧偵増偭偰嵭奞偑偁傝丄捗抧撪偱偼丄壠壆搢夡丂50屗丄敿夡丒戝彫攋丂456屗丄捗攇侾倣丄13屗怹悈丄怹悈乮悈揷乯丂179.3ha丄揇傆偒丂4.3ha偱偁偭偨偲曬崘偝傟偰偄傞乮攡尨丒惣揷丄1955丄嶰廳導婽嶳應岓強丄1955丄捗巗丄1980乯丅偙傟傜旐奞忬嫷偐傜丄捗攇偺婯柾丄姤悈柺愊側偳偼丄曮塱抧恔偺傎偆偑丄埨惌搶奀抧恔傛傝戝偒偐偭偨偙偲偑傢偐傞丅
崱夞偺挷嵏抧揰偑丄偙傟傜捗攇偵傛偭偰姤悈偟偨壜擻惈偑偳偙傕嫮偟丄暚嵒尰徾傕偁偭偨偙偲偑妋擣偝傟偰偄傞偑丄奺抧揰偱偳偺傛偆側懲愊嶌梡傪傕偨傜偟偨偐偼丄晄柧側揰偑懡偄丅慜弎偺傛偆偵乮係乯奀娸挰偱偼丄柧敀側捗攇憌偑擣掕偝傟偟丄偳偺抧揰傕戝偒側懲愊娐嫬偺曄壔傪婰榐偟偰丄偦偺梫場偵捗攇偺傛傞曄壔偲偺峫偊傜傟偨丅偙偺傛偆側抧宍曄壔傪敽偆傛偆側娐嫬曄壔偼丄崱夞偺挷嵏抧揰偱偼1夞偱偁傝丄偙傟傑偱偺嵟戝媺偺捗攇偵傛傞傕偺峫偊傞偲丄傗偼傝柧墳抧恔乮1498乯偺捗攇偵傛傞抧曄偲悇榑偝傟傛偆丅
傑偨丄崱捗嘆偱妋擣偟偨暚嵒峔憿偑丄傕偟偙傟傜抧恔偵傛傞傕偺偲偡傟偽丄柧墳抧恔埲崀偺敪惗偱偁傠偆丅
拞悽偺埨擹捗偵娭偡傞奊恾偑側偄偨傔丄偦偺摉帪偺挰傗柀側偳偺娐嫬傪抧棟揑偵暅尨偡傞偵偼丄偐側傝崲擄偱偁傞丅偦偺偨傔丄偝傜偵峫屆妛揑帒椏偑憹偊丄摉帪偺抧宍娐嫬側偳傪尰戙偺抧宍傗屆抧恾傗抧宍恾丒峲嬻幨恀偱悇掕偟側偑傜丄崱夞偺僕僆僗儔僀僒乕挷嵏偺傛偆側昞憌抧幙偺峀斖側夝柧偐傜丄悇掕偡傞曽朄偑傕偭偲傕桳岠偱偁傞偲巚傢傟傞丅
偙偺拞悽丒埨擹捗偺抧宍暅尨偺偨傔偵偼丄偦偺屻偺抧宍夵曄傪徻嵶偵専摙偡傞昁梫偑偁傞丅偲偔偵埨擹捗忛寶愝乮1558擭埲崀乯傗嬤悽忛壓挰宍惉偐傜尰戙傑偱偺搚抧夵曄傪峕屗婜偺奊恾傗柧帯俁侾擭偵嵟弶偵嶌惉偝傟丄偦偺屻偵廋惓偝傟偨抧宍恾椶乮恾 侾乯丄戝愴埲屻偵嶣塭偝傟偨嬻拞幨恀椶傪棙梡偟偰専摙偟偨丅
傑偨丄偙傟傑偱嶌惉偝傟偨抧宍暘椶恾傗抧幙恾丄抧幙儃乕儕儞僌帒椏側偳偺挷嵏尋媶傪嶲峫偵偟偰丄崱夞偺僕僆僗儔僀僒乕偵傛傞抧幙挷嵏寢壥偵婎偯偄偰丄拞悽偺埨擹捗偺暅尨傪帋傒丄柧墳抧恔埲屻偺抧宍曄壔偵偮偄偰梊嶡偟偰傒偨偄丅
偙偺抧宍暅尨偺億僀儞僩偼丄摉帪偺奀娸慄傪偳偙偵偡傞偐偱偁傞丅師偵偼丄埨擹愳丒娾揷愳側偳偺媽壨摴偲壨岥埵抲偺摿掕傗曄慗偱偁傞丅偝傜偵丄廤棊埵抲偑偁偭偨嵒廈乮嵒懲乯偺旝崅抧偺惓妋側暅尨傗丄姳戱傗惙搚傗杽傔棫偰側偳偵傛傞抧宍夵曄偱偁傞丅側偍丄側偍摗摪崅屨擖晎埲屻偺嬤悽忛壓挰埲屻偺搒巗宍惉巎傗嵭奞巎側偳偵偮偄偰偼丄亀捗巗巎亁側偳偐傜専摙偱偒傞晹暘偑懡偄丅
偙偺暅尨恾偺嶌惉偵娭偟偰偼丄埲壓偺僥乕儅偵偦偭偰峫嶡偟偨偄丅
匑柀偺抧宍
埨擹愳側偳偺彫婯柾側嶰妏廈惈暯栰偺壂愊掅抧偵埵抲偡傞埨擹捗偼丄埳惃榩増娸偺奀昹晹偵偱偒偨屆戙偐傜偺峘榩偱偁傞偐傜丄抧宍揑偵偼壨岥晹偺妰屛偵尷掕偝傟傞丅偦傟偼丄亀捗巗巎亁戞1姫偵婰偝傟傞傛偆偵乽恔嵭埲慜偺埨擹捗峘偼墦偔撍弌偟偨嵒掔偵書岇偝傟偨戝婯柾側帺慠揑峘榩偑丄揔搙偺悈怺傪桳偟偨揤慠偺椙峘偱偁偭偨偺偱丄偙偺嵒掔偑偦偺愄埨擹徏尨偲偄偭偰丄壧恖偺巀旤偺揑偲側偭偨彑宨偱偁偭偨丅乿乮俈暸乯偲傕昞傢偝傟傞丅嬤悽傑偱偺柀偺抧宍忦審偼丄捁塇傗揑栴側偳偺傛偆側儕傾僗幃奀娸榩墱偺揤慠椙峘偺傎偐丄埳惃榩偺傛偆側奀昹晹偱偼丄偙偺傛偆側妰屛傗壨岥柀偱偁傝乮埳摗丄1998乯丄拞悽偵偼埳惃榩丒懢暯梞奀塣偺拞怱偵偁偭偨埨擹捗乮栴揷丄侾俋俋俉乯傕丄偦偺揟宆偱偁偭偨偲巚傢傟傞丅
偙偺壨岥晹晅嬤偵嵒歿傗嵒廈偑怢傃偰奀昹丒昹掔乮偙偺嵒掔偵憡摉乯傪側偟丄埨擹徏尨偑偁傝丄偐側傝恖堊揑偵埨掕壔偟偨奀娸偱丄偦偺撪懁偵廙攽傝偲側傞妰屛丄揤慠偺椙峘偑偁偭偨偲峫偊傜傟傞偑丄婫愡偵傛偭偰偼壨岥側偄偟榩岥偑嵒偱暵嵡偝傟偨傝丄崅挭丒峖悈側偳偱壨岥埵抲傗昹掔偺徏尨偺曄壔傕偁偭偨偲巚傢傟傞丅
匒埨擹愳丒娾揷愳偺棳楬丒壨岥
拞悽傑偱偺埨擹愳側偳偺壨岥偁傞偄偼榩岥偺埵抲傪摿掕偡傞偙偲偑丄奀娸慄埵抲偺妋掕偲崌傢偣偰丄戞堦偺壽戣偱偁傞丅崱擔丄埨擹愳乮搩悽愳乯偺壨岥偑丄巙搊栁愳乮晹揷愳乯偲側傜傫偱丄徏杮嶈偵妋掕偟偨偺偼丄姲惌擭娫乮1789乣1800乯偺徏杮嶈怴揷乮尰嵼偺椉壨岥娫偵偁傞掅幖抧乯偺寶愝偵偲傕側偆搩悽愳壓棳偺慳捠岺帠偺姰惉傗丄摨帪婜偺娾揷愳峘岥偺奐敪惍旛傗奀娸掔杊偺寶愝偱偁傝丄偦傟埲慜偼娾揷愳埲杒偐傜拞壨尨堦懷偼丄埊尨側偳偺掅幖抧偱偁偭偨乮攡尨丒惣揷丄1954乯丅
尰嵼偺埨擹愳偼丄恾侾偺傛偆偵JR揝嫶傪嫬偵偟偰丄忋棳偼帺慠掔杊傪壨娸偵幹峴壨愳偺宍懺偱丄傎傏帺慠偺壨愳偲尒傜傟傞偺偵懳偟丄壓棳懁偱偼杒搶曽岦偵岦偒傪曄偊丄傎傏捈慄偵嬤偄宍懺偱丄徏杮嶈偺壨岥傑偱楢懕偡傞丅偙偺嵟壓棳晹偼丄壨娸偵帺慠掔杊偺敪払偑埆偔丄傑偨捈慄忬偐傜丄慜弎偺傛偆偵徏杮嶈怴揷埲崀偺恖岺揑側棳楬偲峫偊傜傟傞丅
媽抧宍恾乮恾 侾乯偐傜柧傜偐側傛偆偵丄埨擹愳塃娸偐傜拞壨尨丄嫜嶈乮尰娾揷愳壨岥乯偵尰奀娸慄偵幬岎偡傞傛偆偵暘晍偡傞丄堦楢偺嵒抧偺旝崅抧偑偁傞丅偦偺堦晹偼嵒廈偺壜擻惈傕偁傞偑丄帺慠掔杊偲偺暋崌偲巚傢傟丄埨擹愳媽壨摴偑偦傟偲壋晹偺旝崅抧偲偺娫偵偁偭偨偙偲傪埫帵偝偣傞丅姲惌擭娫乮侾俉侽侽擭慜屻乯偺搩悽愳壓棳偺慳捠岺帠傑偱偼丄偍偦傜偔丄偙偺儖乕僩偑埨擹愳偺暘棳偲傕側偭偰偄偨偲巚傢傟傞丅傑偨丄奀娸挰乮係乯僒儞僾儖偺捗攇憌忋晹偺斆棓尨懲愊暔偼丄偦偺埨擹愳偺媽棳楬偵傛傞傕偺偐傕偟傟側偄丅
JR揝嫶偺偡偖惣懁偼媽屆愳懞乮尰屆壨挰乯偲屇偽傟丄埲慜偵埨擹愳偑崱傛傝撿懁乮塃娸懁乯偵偁偭偨偲偄傢傟丄傑偨捗忛偺杒杧傗撿杧偺椉奜杧偲傕媽埨擹愳棳楬傪棙梡偟偨偲偄傢傟傞丅偲偔偵撿杧偼丄亀嶰廳導偺抧柤亁偺乽撿杧抂乿崁偱丄乽拞悽偵偼丄埨擹愳偺暘棳偑丄孻晹懞丄屆愳懞傪宱偰丄幬傔偵屻傠偺撿奜杧傪棳傟檩杧晅嬤偱娾揷愳偲崌棳偟偰偄偨乿偲偟偰乮暯徏丄1983乯丄埨擹愳偺暘棳乮庡棳偐乯偑崱偺娾揷愳偲側偭偰偄偨傛偆偩丅
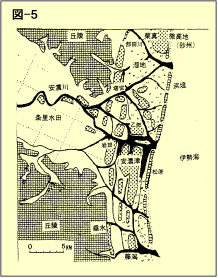
尰嵼偺娾揷愳壨岥偼丄偙偺暯栰堦懷偺拞偱偼壂愊憌偺岤偝偑嵟戝偱偁傝丄栺俀俆倣埲忋俁侽倣枹枮偵払偡傞丅偦偺俀侽倣埲忋偺憌岤暘晍偺摍抣慄乮捗巗丄侾俋俉侽偺恾俆乯偑丄壨岥偐傜忋婰偺撿杧丄屆愳懞偺媽埨擹愳偺棳楬傪傎傏堦抳偟偰偄傞偐傜丄撽暥奀恑埲慜偐傜埨擹愳偺杮棳偼丄捗忛抸忛埲慜傑偱丄偙偺儖乕僩偵偁偭偨偲悇掕偝傟傞丅
匓拞悽婜偺媽奀娸慄偼偳偙偵
媽奀娸慄偼丄拞悽偐傜尰戙傑偱傎偲傫偳奀柺偺曄摦偑側偄偲壖掕偱偒傞偐傜丄忋棳偐傜偺搚嵒嫙媼偵傛傞奀懁傊偺慜恑傗丄捗攇丒崅挭側偳偺怤怘偵傛傞屻戅丄偝傜偵偼帺慠怉旐傗恖堊揑怉椦側偳偵傛傞奀昹屌掕壔偑恑傫偩傕偺偱偁傞丅姲惌擭娫乮侾俉侽侽擭慜屻乯偺娾揷愳偺壨岥惍旛丄徏杮嶈怴揷丄搩悽愳壓棳偺慳捠岺帠側偳偲娭楢偟丄尰奀娸慄偑丄掔杊傪抸偒怉嵧側偳偱屌掕壔偝傟偨傛偆偱偁傞乮攡尨丒惣揷丄1954丄楅栘丄1998乯丅
偟偐偟忦棦搚抧惂偺斖埻偐傜丄撧椙帪戙偺媽奀娸慄偺埵抲傪暅尨偡傞曽朄偑偁傞乮扟壀丄侾俋俇係乯丅偙偺抧堟偺忦棦峔憿偼丄恾侾偺柧帯31擭斉抧宍恾偺堦晹偵帵偝傟偰偄傞傛偆偵丄捗忛愓惣懁偺悈揷傗挰暲傒乮敧挰乯偺摴楬偐傜傕柧椖偵妋擣偱偒傞丅捗忛偺孈妱傗堦晹偺挰妱傕偙偺忦棦偲摨偠曽埵乮N侾侽亱E丄杒偐傜侾侽搙搶偺曽岦乯傪偲傞偙偲偑丄偙傟傪婎弨慄偵偟偨傕偺偱偁傞丅
偙偺忦棦偺杒惣抂偵拞壨尨傪娷傓堦忦堦搩悽棦偑偁傝丄偦偺杒惣抂偑丄傎傏尰奀娸慄偵埵抲偟偰偄傞乮栱塱丒扟壀丄侾俋俈俋乯偺偱丄屆戙偐傜傎傏尰奀娸慄偲摨偠埵抲偵偁偭偨悇掕偝傟傞丅尰巙搊栁愳壨岥埲杒偺奀娸慄偑丄嵒廈偲側偭偰偍傝丄壨岥埲撿偵捈慄忬偵楢懕偡傞偙偲偐傜丄屆戙偐傜奀娸慄埵抲偼丄傎偲傫偳曄壔偟側偐偭偨偲峫偊傜傟傞丅 偡側傢偪丄埨擹捗偺柀傪埻傓傛偆偵丄奀懁偵偁偭偨掔杊忬偺嵒歿乮埨擹徏尨乯偺奀娸慄偼丄傎傏尰嵼偺埵抲偵偁偭偨偲悇榑偱偒傞丅
拞悽丒埨擹捗偺徚柵偵娭偟偰丄亀捗巗巎亁戞1姫偱偺乽捗峘娮杤乿偱偼丄乽偙傟乮拲丒埨擹徏尨乯偑丄恔嵭偺偨傔偵慡晹奀拞偵杤偟丄偦偺忋奀娸堦懷偺擃庛側怴抧憌傕枖嫟偵娮杤偟偰偟傑偭偨偺偱偁傞丅乿乮俈暸乯偲偟偰丄抧斦偑娮杤偵傛傞柀偑徏尨偲傕偵奀拞偵徚偊偨偲悇榑偟偨乮攡尨丒惣揷丄1954乯丅偦偺偨傔丄埨擹徏尨傗柀偺妰屛偑丄尰奀娸慄偺壂懁偵偁偭偨偲丄亀捗巗巎亁摨條偵峫偊傜傟偰偒偨乮堥晹丄1984丄楅栘丄1998乯丅
崱夞偺俁抧揰偺僒儞僾儖偐傜丄捗攇懲愊暔偼妋擣偝傟側偐偭偨偑丄奀娸挰乮係乯偺抧揰偐傜偼丄柧妋側捗攇憌偑敪尒偝傟偰偄傞丅帪戙偼傑偩晄徦偩偑丄偙偺柧墳抧恔偺壜擻惈偑崅偄丅偦偟偰丄娮杤傗抧妸傝忬偺奾棎懲愊暔偼丄偳偺僒儞僾儖傗丄桍嶳偺堚愓抐柺側偳偐傜偼丄慡偔妋擣偝傟側偐偭偨丅
傑偨崱捗乮侾乯偺抧揰昗崅亅侾丏俉倣丄寢忛恄幮乮俁乯偺昗崅亅侾丏侾倣偱丄撪榩娐嫬偐傜奀昹娐嫬偵曄壔偟偨偙偲偑嫟捠偟偰擣傔傜傟偨丅偙偺娐嫬曄壔偺梫場偼丄壂懁偺埨擹徏尨偺傛偆側掔杊忬偺嵒歿偑徚幐偟偨偨傔偲巚傢傟丄扨偵娮杤傛傝戝偒側捗攇偱攋夡偝傟丄妰屛偑奀昹壔偝傟傕偺偲悇榑偝傟傞丅
偙偺擇抧揰偼丄偦偺撪榩娐嫬偺摉帪偵偼悈怺偑栺1乣俀倣偁偭偨偨傔丄偦偙偺揇傗嵶嵒偺捈忋偵丄慹棻壔偟偨嵒憌偑捗攇偵傛偭偰懲愊偟偨傕偺偱偁傠偆丅捗攇偵傛傝埨擹徏尨丄妰屛丄嵒廈忋偺挰暲傒側偳偺懡偔偑棳幐偟丄奀昹偑偙偺嵒廈嬤偔偵傕敆偭偨偨傔丄慡懱偵乽娮杤乿偟偨傛偆偵岆夝偝傟偨偨傔偲峫偊傜傟傞丅
偝傜偵埨擹捗桍嶳堚愓偺傛偆偵挰暲傒偺徚幐傗亀廆挿庤婰亁乮侾俆俀俁乯偺婰弎傪傒傞偐偓傝丄偙偺奀娸晹偑丄抧恔偱壓曽偵捑壓偟偨傝丄奀懁偵抧妸傝偟偰徚幐偟偨傕偺偱側偔丄捗攇偵傛傞尨場偑庡懱偱偁偭偨偲峫偊傞偺偑揔摉偱偁傠偆丅
慜婰偟偰偒偨傛偆偵丄埨擹捗偺柀偼丄尰娾揷愳晅嬤偵偁偭偨埨擹愳壨岥偺妰屛偵偁偭偨偟丄摉帪偺奀娸慄傕傎傏尰嵼偲摨偠埵抲偵偁傝丄偦偙偑埨擹徏尨偱偁偭偨偲悇掕偟偨丅徏尨偺愗傟栚偱偁傞榩岥偺埵抲偵娭偟偰偼丄奀娸挰僒儞僾儖偺捗攇憌偺懚嵼偐傜丄偙偺抧揰偑丄懠偺僒儞僾儖抧揰偵斾傋丄捗攇偵傛傞怤怘傕偁傞偐傜丄榩岥偐傜捗攇偑捈愙偵偁偨傞埵抲偵偁偭偨偲偡傞偲丄尰娾揷愳壨岥偐丄傢偢偐偦偺杒懁偵榩擖岥偑偁偭偨偲梊憐偝傟傞丅
柧帯婜偺媽抧宍恾偱傕柧傜偐側傛偆偵丄壋晹偺旝崅抧撿懁偺娾揷愳嵍娸偵掅幖抧偑丄媽埨擹愳壨岥偐偦偺妰屛偱偁偭偨丅崱捗乮侾乯僒儞僾儖偐傜傕丄悈怺俀倣傎偳偺妰屛偑偁偭偨偙偲偑妋偐傔傜傟偨偟丄桍嶳堚愓偺偡偖搶懁偵埵抲偡傞偙偲偐傜丄偙偺戃忬偺妰乮偺偪偺柀揷乯偑柀偺堦晹偺壜擻惈偑偁傞丅
傑偨丄媽抧宍恾偐傜傕敾柧偡傞傛偆偵丄桍嶳偲娾揷偺嵒廈丒旝崅抧偺娫偵峀偄掅幖抧偑戃忬偵暘晍偡傞偑丄峕屗弶婜偵寶愝偝傟偨杧愳偺慏攽傝偺撿懁偱偁傞偐傜丄偙偙傑偱妰屛偺柀偑偁偭偨偲傕峫偊傜傟丄崱屻偺帋孈偵傛傞妋擣偑朷傑傟傞強偱偁傞丅
幍棦乮1992乯偼丄彫帤抧柤傪傕偲偵偟偰丄尰垻憜墂偺搶偵丄乽憜乿丄乽擖峕乿丄乽壔徬乿側偳偑偁傝丄尰娾揷偺旝崅抧偵挰暲傒偑偁傝丄敧敠恄幮乮寢忛恄幮偺偲側傝乯偺搶懁偺奀娸嬤偔偵偁傞乽杮岥乿偁傞偺偱丄偦偙偑榩岥偲悇掕偟丄偦偙偐傜乽擖峕乿乽憜乿偑丄埨擹捗偺柀偲峫嶡偟偨丅偙傟傜抧柤偑丄拞悽埲慜偐偺妋徹偑柧傜偐偱側偄偱晄柧偩偑丄帵嵈偵偲傓採埬偱偁傞丅
崱夞偺寢忛恄幮偺僒儞僾儖偱傕丄悈怺侾倣傎偳偺妰屛偑偁傝丄偙偺撿偵摗曽乮摗妰乯偺抧柤偺傛偆偵丄偙偺撿懁偵傕峀偄妰屛偑偁偭偨偑丄偙偙偲桍嶳傗娾揷偺挰暲傒嬤偔偺柀偲楢寢偟偰偄偨偐偼丄尰抜奒偱偼敾抐偱偒側偄偑丄悈楬偑偙偺掅幖抧偵傕偁偭偨壜擻惈偼廫暘峫偊傜傟傞丅崱屻偝傜偵丄峀斖埻偺帋孈挷嵏偑恑揥偡傟偽丄埨擹捗柀偺暅尨憸偑妋偐側傕偺偵側傠偆丅
埲忋偺傛偆側専摙傪摜傑偊偰丄恾俆偵拞悽丒埨擹捗偺暅尨傪帋傒偨寢壥傪採帵偟偨丅
嶲峫暥專
堥晹 崕乮侾俋俉係乯捗巗奀娸偼夁嫀偵捑杤偟偨丄捗惣崅婭梫丄俇崋丄侾乣5
埳摗桾執乮侾俋俋俈乯拞悽偺峘榩搒巗丒埨擹捗偵娭偡傞妎彂丄亀傆傃偲亁丄49崋丄1乣22
埳摗桾執傎偐乮侾俋俋俈乯亀埨擹捗亁丄嶰廳導杽憼暥壔嵿挷嵏曬崘彂丄147丄182p
埳摗桾執乮侾俋俋俉乯埨擹捗尋媶偺尰忬偲壽戣丄Mie history, 俋丄35乣46
堫杮婭徍乮侾俋俉俋乯擔杮嶰捗偵娭偡傞巎椏偺尋媶丄捗巗巗挿岞幒丄45p
攡尨嶰愮丒惣揷廳巏乮侾俋俆係乯亀捗巗巎亁戞侾姫丄捗巗栶強丄俉侽俆倫
攡尨嶰愮丒惣揷廳巏乮侾俋俆俆乯亀捗巗巎亁戞俀姫丄捗巗栶強丄俉侽侽倫
寶愝徣崙搚抧棟堾乮侾俋俇俋乯搚抧忦審挷嵏曬崘彂乮埳惃榩惣晹抧堟乯丄侾侽侽倫
幍棦婽擵彆丒弎乮侾俋俋俀乯埳惃榩暔岅丄捗偺傎傫丄37崋丄68乣73
楅栘偟偘傞乮侾俋俋俉乯埨擹捗偺柀偼娮杤偟偨偐丄巹壠斉丄60p丄
崅揷孿懢乮侾俋俋俋乯嶰廳導増娸掅抧偺捗攇嵭奞偲旝抧宍丄峀搰戝妛戝妛堾暥妛
尋媶壢丄廋巑榑暥丄112p
扟壀晲梇乮侾俋俇係乯亀暯栰偺奐敪亁丄屆崱彂堾丄俁係係倫
捗巗乮侾俋俉侽乯捗巗抧斦抧幙挷嵏曬崘彂丄侾侾俉倫
捗偺儖乕僣傪扵傞夛乮侾俋俋俉乯亀埨擹捗峘尋媶亁丄捗偺傎傫暿嶜丄170倫
拞揷丂崅丒搰嶈朚旻乮侾俋俋俈乯妶抐憌尋媶偺偨傔偺抧憌敳偒庢傝憰抲乮Geo-slicer乯丄
抧妛嶨帍丄侾侽俇姫丄侾崋丄俆俋乣俇俋
惣拠廏恖傎偐乮侾俋俋俇乯昹柤屛廃曈偺捗攇懲愊暔偐傜扵傞夁嫀偺搶奀壂抧恔丄
柤屆壆戝妛壛懍婍幙検暘愅寁嬈愌曬崘彂丄嘮丄193乣203
暯徏椷嶰傎偐乮侾俋俉俁乯亀嶰廳導偺抧柤亁丄暯杴幮丄1081p
嶰廳導乮侾俋俋侽乯搚抧暘椶婎杮挷嵏乽捗惣晹乿乽捗搶晹乿乮5枩暘偺侾乯丄係侾倫
嶰廳導婽嶳應岓強乮侾俋俆俆乯亀嶰廳導嵭奞巎亁丄侾俈侽倫
栚嶈栁榓乮侾俋俉俋乯乽埨擹捗峘乿専徹丄捗偺傎傫丄俀俋崋丄18乣27
栴揷弐暥乮侾俋俋俇乯柧墳抧恔偲峘榩搒巗丄擔杮巎尋媶丄412崋丄31乣52
栱塱掑嶰丒扟壀晲梇曇乮侾俋俈俋乯亀埳惃榩抧堟偺屆戙忦棦惂亁丄搶嫗摪弌斉丄319p
巐曽峅崕乮侾俋侾俀乯捗巗偺抧曄丄嶰廳導巎択夛乆帍丄3姫10崋丄601乣605
搉曈執晇乮1985乯亀擔杮旐奞捗攇憤棗亁丄搶嫗戝妛弌斉夛丄俀侽俇倫
|