|
丂乽埨擹捗峘乿偲偼丄尰嵼偺娾揷愳壨岥晅嬤偵拞悽傑偱偁偭偨偲偝傟傞峘偱偡丅
丂侾係俋俉擭丄柧墳偺抧恔偵傛偭偰戝偒側旐奞偵憳偄丄抧宍偺曄壔偵傛偭偰姰慡偵偦偺婡擻傪幐偭偨偲偝傟傑偡偑丄楌巎揑帒椏偑傎偲傫偳側偔丄偦偺応強偼傕偪傠傫丄婯柾傕慡偔晄柧偱偡丅乽捗偺儖乕僣傪扵傞夛乿偼丄偦偺峘傪堦斒巗柉丄偝傜偵偼廃曈偺恖払偵傕僀儊乕僕偱偒傞傕偺偵偟偨偄偲峫偊丄敪懌偟傑偟偨丅侾俋俋俆擭廐偺偙偲偱偡丅
丂偙偺僌儖乕僾偺拞妀偼丄侾俋俉俁擭憂姧偺丄嫿搚帍乽捗偺傎傫乿傪嶌傝懕偗偰偒偨恖払偱偡丅偦偺乽捗偺傎傫乿偱乽埨擹捗峘傪扵傞乿乮1989擭6寧崋乯偲偄偆摿廤傪偟偨偙偲偑偁傝丄埲棃丄擭偵悢夞15乣20悢恖偑廤傑傞乽堸傒夛乿偱偼忢偵榖戣偵偁偑傝丄乽捗偺傎傫乿偺恖払偺婥偵側傞僥乕儅偱傕偁傝傑偟偨丅
丂拞偱傕嶰廳戝妛恖暥妛晹嫵庼丒栚嶈栁榓偝傫偼嫮椡側乽孈偭偰尒傛偆傛乿悇恑榑幰偱丄奀梞抧棟偺挷嵏摍偱悽奅偺崙乆丄峘挰傪夞傞偆偪丄嫃偰傕棫偭偰傕嫃傜傟側偔側偭偨傜偟偔丄僯儏乕僕乕儔儞僪偐傜乽夡柵屲昐擭偼嶰擭屻丄偝偁乕孈傠偆両乿側傫偰偄偆俥俙倃傪曇廤幒偵憲傝偮偗偰偔傞傎偳偺擬偺擖傟傛偆偱偁傝傑偟偨丅
丂乽捗偺傎傫乿偼捗傪傆傞偝偲偲偟丄偦偙傪傛偔抦傞偙偲偵傛傝丄傛傝垽拝傪帩偭偰曢傜偡偨傔偺嶨帍偱偁傝懕偗偰偒傑偟偨丅摿廤偺僥乕儅偼丄巹偨偪偺廧傓応強偺乽曢傜偟乿乽楌巎乿乽尵梩乿偱偁傝丄乽擔忢偺婰榐乿偱偁傝傑偡丅偮傑傝丄傆傞偝偲偺傾僀僨儞僥傿僥傿乕偺妋擣偱偁傝丄乽埨擹捗乿偲偄偆峘偼捗偑捗偱偁傞偲偄偆偙偲偺寚偐偡偙偲偺弌棃側偄憑偟暔偱偁偭偨傢偗偱偡丅
丂偦偆偄偆攚宨偺拞偐傜乽捗偺儖乕僣傪扵傞夛乿偑弌棃丄曌嫮夛偑巒傑傝傑偟偨丅夛堳偲偟偰62柤偑廤傑傝傑偟偨丅
丂偙偺曌嫮夛偺婰榐偼乽捗偺傎傫暿嶜亀埨擹捗峘尋媶亁乿乮1998擭俇寧敪峴乯偲偟偰傑偲傔傑偟偨偺偱丄偙偙偱偼偦偺奣梫傪徯夘偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅
丂捗偼偦偺傕偺偢偽傝乽峘乿偲偄偆堄枴偺娍帤偱偡偑丄埨擹捗偲偄偆抧柤偑帒椏忋偵弶傔偰昞傟傞偺偼侾侾悽婭偺枛丄嫗搒偺岞壠偺乽拞塃婰乿偲偄偆擔婰丅
丂塱挿尦擭乮1096擭乯丄抧恔偱戝捗攇偑婲偙偭偰埨擹捗偺柉壠偑懡悢懝夡偟偨偲偄偆婰帠偱偡丅
丂偦傟埲屻丄抧恔偲偄偆偺偼壗夞傕偁偭偨偺偱偟傚偆偑丄戝偒側旐奞偲偄偆偺偼柧墳偺抧恔丅偲偔偵柧墳俈擭乮1498擭乯俉寧25擔偺傕偺偱丄儅僌僯僠儏乕僪8.2乣8.4偲悇應偝傟丄偨傫偵僄僱儖僊乕偱斾妑偡傞偲丄愭偺嶃恄恄屗抧恔偺栺30攞丅昹柤屛偑奀偲偮側偑傝丄埳惃偺戝柀偑俇乣俉儊乕僩儖丄捗偱傕彮側偔尒愊傕偭偰俁乣係儊乕僩儖偺捗攇偑敪惗偟偨偲偝傟偰偄傑偡丅嶰壨丄弜壨丄墦峕丄婭埳偐傜朳憤堦懷傕旐奞傪庴偗丄峘偲偟偰偼丄弜壨彫愳柀丄婭埳榓揷塝丄墦峕嫶杮丄側偳偑夡柵偟偨偲偺婰榐偑巆偝傟偰偄傑偡丅偟偐偟埨擹捗偺偙偲偼丄亀屻朄嫽堾婰亁偺柧墳幍擭偺忦偵揱暦偲偟偰乽乧埳惃嶰壨弜壨埳摛偵戝捗攇懪偪婑偣乧丄慜戙枹暦偺帠栫乧乿偲埨擹捗偺嬶懱揑側婰弎偼側偔丄抧恔屻25擭丄偙偺抧傪朘傟偨楢壧巘丒廆挿偑丄乽崯捗廫梋擭埲棃峳栰偲側傝偰丄巐丒屲愮尙偺壠丒摪搩愓偺傒丅愺姖丒朒乮傛傕偓乯偑瀃乮偦傑乯丄惤偵寋將偼傒偊偢丄柭殡乮傔偄偁偄偐傜偡乯偩偵婬側傝丅乿乮廆挿庤婰1523擭-亀廆挿擔婰亁娾攇暥屔乯偲巆偟偰偄傞偺傒偱偁傝傑偡丅
丂偦偺屻丄埨擹捗偑尰傟傞偺偼丄16悽婭偵側傝丄拞崙偺柧偺帪戙丄榓檓偵懳偡傞懳嶔丄杅堈憡庤偲偟偰偺擔杮傊偺娭怱偑崅傑傝丄偦偺壽掱偱丄擔杮偵娭偡傞婰弎丄杮傕嶌傜傟偰偄偔拞偱丄層憊寷偲偄偆恖偑彂偄偨亀庠奀恾曇乮偪傘偆偐偄偢傊傫乯亁乮1561擭乯偑偁偘傜傟傑偡丅
丂乽婭埳偺惣傪埳惃偲偄偆丅
丂杒偼嶰壨丄偦偺墱傪崢戝乮傛偳亖戝梽偐乯偲偄偄丄垻擳搝巕偲偄偆乧丅乿
丂偙偺乽巕乿偼乽僣乿偲敪壒偡傞偺偱傾僲僲僣丄偙傟偼柧傜偐偵埨擹捗偲峫偊偰偄偄傢偗偱丄偙傟偑拞崙偺暥專偵弶傔偰搊応偡傞埨擹捗偲側傝傑偡丅
丂偦傟偐傜亀擔杮晽搚婰亁乮1591擭丒岓宲崅挊乯丄偁傞偄偼亀擔杮峫亁丅偝傜偵偦傟偼亀晲旛巙亁乮1621擭丒姖尦媀挊乯偵庴偗宲偑傟偰偄偒傑偡丅
丂嫟捠偡傞撪梕偼丄
丂乽崙偵嶰捗偁傝丄奆奀偵捠偢傞峕乮偄傝偊乯偵偟偰丄彜慏壿暔偺廤阙偡傞偲偙傠偱偁傞丅惣奀摴偵偼朧捗抧曽偑偁傝丄峕偁傝偰丄奀偵捠偠丄嶧杸廈偺強懏偱偁傞丅壴埉搩捗乮偼偐偨偺偮乯傕峕偁傝偰丄奀偵捠偠偰丄拀慜廈偺強懏偱偁傞丅搶奀偵偼摯捗偐偁傞丅偙偺崙偺嫿壒偵偰偼乽垻擳師乿偲偄傆丅捗傪乽師乿偲屇傇偙偲丄偙偺椶偱偁傞丅峕偁傝偰奀偵捠偠丄埳惃廈偺強懏偵偐偐傞丅偙傟傜嶰捗偼丄擳偪恖墝鐂廤偺抧偱偁傝丄偄偯傟傕奺強偺斪偵捠偢傞丅彜壿乮嫔乯偺廤傑傞偲偙傠偱偁傞丅乮拞棯乯嶰捗偺拞丄朧捗偺傒傪憤楬偲側偟丄媞慏偺墲曉偵偼昁偢崯偺抧傪夁偓傞丅帶偟偰壴埉搩捗偼拞捗偱偁傝丄抧曽峀弫丄恖墝鐂廤偟偰丄彜傆傕偺丄暔偲偟偰旛傜偞傞偼側偄丅摯捗偼枛捗偱偁傝丄偦偺抧曽丄枖墦偔丄嶳忛偺嫗搒偲憡嬤偄丄壿暔偼埥傞傕偺偼旛傝丄埥傞傕偺偼寚偒丄堦抳偟側偄丅乿偲偁傝傑偡丅
丂崙撪偱偼丄柧楋擇擭乮1656擭乯乯偺亀惃梲嶨婰亁丅
丂乽乧乧柧墳擭拞偺抧恔埲慜偵偼捗挰偲奀偲偺娫偵屆傝偨傞徏尨桳偲塢丄懘偺徏尨擖峕怺偔慏偐乀傝枖墲棃偺曋傝媂偒柀側傝偗傞偵抧恔偺帪攋媝偟偰徏尨偲嫟偵愓曽傕側偔柀傕墦愺偵懼傝帢傞偲塢乆乿偲彂偐傟偰偁傝丄偮偯偄偰丄揤曐係擭乮1833擭乯偺亀惃梲屲楅堚嬁亁丅
丂偙偙偵偼乽惃梲晎巙塢埨擹捗偲奀偲偺娫偵徏尨偁傝偰偙傟傪埨擹徏尨偲塢柧墳幍擭偺戝抧恔偵忛壓傕徏尨傕楺偺堊偵捑傔傝丄崱徻偵偡傞偵屻搚屼栧揤峜柧墳幍擭榋寧廫擔峖楺偵晎壓偺柉壆傕廫嬨挌嫋捑杤偟偨傞偼墦峕昹徏峳堜崱愗偺徛偵曄偟偨傞偲摨帪側傝丄埥偼塢枩帯尦擭峖攇偵熚杤偡偲塢傆偼屻恖偺壇抐側傝乧乧乿丄偁傞偄偼亀惃梲屲楅堚嬁亁乮1833擭乯丄亀埳惃巙棯乮1984擭乯丄亀惃梲峫屆榐亁亀嬨揷埗摪悘昅棖恛亀嶨廤婰亁亀憪堻嶜巕亁側偳偵傕丄摨偠傛偆側婰弎偑偁傞丅
丂偟偐偟丄偙傟傜偼偐側傝帪戙偑壓偭偰偐傜偺傕偺偱偁傝丄埨擹捗峘偺拞悽傑偱偺惗偒惗偒偲偟偨巔偼揱傢偭偰棃傑偣傫丅
丂恾偼栚嶈栁榓嫵庼偺抧棟揑尋媶惉壥偵埶傝側偑傜丄嶰廳導杽憼暥壔嵿僙儞僞乕妛寍堳丒埳摗桾執偝傫偑嶌惉偟偨埨擹捗偺峘挰偺暅尦恾偱偡丅
丂埨擹愳丄塤弌愳偺搚嵒偑増娸棳偵傛偭偰丄奀娸慄増偄偵懲愊偟丄係忦傎偳偺嵒懲偲側偭偰埨擹捗偺峘挰傪宍嶌偭偰偄傑偡丅嵒懲杒偺埨擹愳壨岥晹偲丄嵒懲偺撿偵懚嵼偟偰偄偨妰屛乬摗妰乮傆偠偐偨乯乭偐傜慏敃偑恑擖偟偰偄傞傕偺偲峫偊傜傟傑偡乮乽埨擹捗尋媶偺尰忬偲壽戣乿Mie history vol.9乯丅偙偺僞僀僾偺奀偲暯峴偟偨撪悈柺偵増偭偰奐偗偨峘偲偄偆忣宨偼丄拞悽偺峘榩搒巗偵懡偔尒傜傟丄愭偵婰偟偨婭埳榓揷塝丄墦峕嫶杮丄弜壨彫愳柀丄偁傞偄偼捗寉偺廫嶰柀乮偲偝傒側偲乯傪戙昞偲偡傞壛夑丄墇屻側偳偺擔杮奀増娸偵傕懡偔尒傜傟傞忣宨偩偦偆偱偡丅
丂偙偺嵒懲偺撪棨婑傝偐傜悢偊偰俀忦栚偺拞怱晹丄桍嶳捗嫽抧撪偺捗幚嬈崅峑乮尰嶰廳柌妛墍乯晘抧撪偱峴傢傟偨乽埨擹捗桍嶳堚愓乿敪孈挷嵏乮1996擭丒嶰廳導杽憼暥壔嵿僙儞僞乕丒庡擟妛寍堳埳摗桾執巵乯偱偼丄偄偵偟偊偺埨擹捗傪渇渋偲偝偣傞悢乆偺堚峔丒堚暔偑妋擣偝傟傑偟偨丅偦偺徻嵶偼摨僙儞僞乕敪峴偺曬崘彂偵傛偭偰偄偨偩偔偲偟偰丄擇偮偺嫽枴怺偄帠椺傪徯夘偟傑偡丅
丂堦偮偼丄廫嶰悽婭拞崰偺嶳拑榦偲懎徧偝傟傞偍傃偨偩偟偄摡婍偺悢乆偱偡丅嶳拑榦偲偼丄垽抦導悾屗巗傗抦懡敿搰丄埈旤敿搰側偳偱嶌傜傟傞從偒暔偱埨擹捗桍嶳堚愓偐傜偺弌搚昳偵偼丄偦偺傎偲傫偳偑枹巊梡偺傕偺偱丄掙晹偵杗彂偒偝傟偨傕偺偑偁傝丄偦偺堦偮偵乽挌栤乿乽挌垻乿乽挌峧乿偺偄偢傟偐偲撉傔傞暥帤偑彂偐傟偰偄傞偙偲偱偡丅
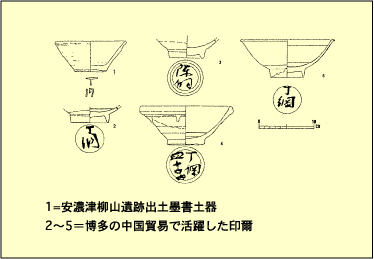
丂偙偺偙偲偼垽抦導偱惗嶻偝傟偨摡婍偑丄惗嶻抧偱慖暿偝傟傞偙偲側偔丄埨擹捗偵塣偽傟丄奺抧傊弌壸偝傟偰偄偨偙偲傪帵偡傕偺偱偡丅掙晹偵婰偝傟偨杗彂偵偮偄偰丄埳摗桾執偝傫偼丄
丂乽乧乽挌栤乿偱偁傟偽丄埨擹捗偵懚嵼偟偰偄偨乽憜挌晹乿偲偄偆恄媨恄恖偑娭傢偭偰偄偨栤偐丄偁傞偄偼乽挌乿偲偄偆恖暔偺娫傪巜偡傕偺偲峫偊傜傟傑偡丅栤偲偼丄摉帪偺奀塣嬈偵実傢傞廤抍傪堄枴偟傑偡丅乽挌垻乿偱偁傟偽丄姪恑惞側偳偵戙昞偝傟傞暓嫵娭學幰偺娭梌偑憐掕偱偒傑偡丅乽挌峧乿偱偁傟偽丄栤戣偼彮偟暋嶨偵側傝傑偡丅乽挌峧乿偲偄偆杗彂偼丄埨擹捗偲摨偠偔乽嶰捗乿偺傂偲偮偲偝傟傞攷懡偱丄拞崙偐傜塣偽傟偰偒偨摡帴婍椶偵悢懡偔妋擣偝傟偰偄傑偡丅埨擹捗偺杗彂偑乽挌峧乿偲偡傟偽丄崙嶻偺摡婍椶偺棳捠偵偝偊拞崙宯偺彜恖偑壗傜偐偺娭梌傪偟偰偄偨偙偲偵側傝傑偡丅杗彂偺暥帤偑偳傟側偺偐偼崱偼抐掕偱偒傑偣傫偑丄埨擹捗偵懚嵼偟偰偄偨乬彜恖乭傜偟偒幰傪峫偊傞偆偊偱丄偙偺杗彂搚婍偼偲偰傕廳梫偱偁傞偲偄偊傑偡丅乿偲弎傋偰偄傑偡丅
丂傕偆堦偮偼丄廫屲悽婭枛崰偐傜廫幍悽婭崰偵偐偗偰丄堚愓偺嬻敀婜偑偁傞偙偲偱丄偙偺偙偲偼丄揱偊傜傟傞柧墳偺恔嵭偺暅嫽婜偵摉偨傞偙偲傪帵偟偰偄傞傛偆偱丄乽廫屲悽婭偐傜廫榋悽婭偵偐偗偰丄杒晲憼偐傜忋栰偺忢妸從偒偺弌搚偑寖柵偟丄忢妸從偒偺嫙媼尦偺峘榩搒巗埨擹捗偺柧墳抧恔偵傛傞夡柵偲偺娭學偑峫偊傜傟傞乿偲偺怴妰戝妛丒栴揷弐暥嫵庼偺乽柧墳抧恔偲懢暯梞奀塣乿乮亀柉廜巵尋媶亁55乯偲屇墳偡傞偙偲偱偡丅
丂堦曽丄愭崰敪孈偝傟偨丄婐栰挰丒曅晹堚愓偺乽杗彂搚婍乿丄埨擹挰丒戝忛堚愓偺乽崗彂搚婍乿摍偵尒傜傟傞戝棨暥壔偲偺娭學傪巚傢偣傞帠椺丄偁傞偄偼捗廃曈偺堚愓丄捗巗戝棦孍揷挰偺巙搊栁愳塃娸幬柺偵峀偑傞乽榋戝俙堚愓乿丄塤弌搰娧堚愓偺乽屆暛暛媢乿摍乆丄偦偙偐傜埨擹愳丄塤弌愳傪慿傞暥壔岎棳嫆揰偲偟偰偺栱惗帪戙偐傜楢柸偲懕偔乽埨擹捗乿偺懚嵼偑晜偐傃忋偑偭偰偒傑偡丅
丂埨擹捗偑偐偭偰峘挰偱偁偭偨偙偲傪帵嵈偡傞堦偮偺庤偑偐傝偲偟偰丄搚抧嬫夋偲抧柤偑偁傝傑偡丅
丂埨擹捗偼柧墳偺恔嵭屻丄峘挰偼偐側傝暅嫽偟偨偲偺宍愓偼偁傞傛偆偱偡偑丄偦偺徚柵偵娭偟偰傕偆堦偮偺梫場偲偟偰丄嬤悽捗忛壓挰偺惉棫偑偁偘傜傟傑偡偑丄偦偺搚抧嬫夋偼拞悽偲嬤悽偱傎偲傫偳堦抳偟偰偄傞偲偙傠偑懡偔丄偦偺堦偮偑丄捗嫽廃曈偺惣棃帥毈偱偁傝丄忋媨帥毈乮尰嵼偺垻憜捤乯側偳偑偁傝丄傑偨斔惌帪戙偺亀捗嫽屘抧恾亁偵傛傞偲丄捗嫽偱偼乽娤壒乿乽戝栧乿乽拞偺斣乿乽廻壆乿偺帤柤偑尰嵼偺巗奨抧偺偦傟偲摨偠弴彉偵暲傫偱偄傑偡丅偦偙偐傜撿傊乽擖峕乿丅垻憜塝奀娸偵偼乽尦岥乿偲屇偽傟傞抧嬫偑偁偭偰丄崱偺寢忛恄幮偺嬤偔偱偁傞傜偟偔丄偦偺傑偨撿丄暷捗偺廤棊偵乽從弌棦乿偲崗傑傟偨旇偑偁傝傑偡丅
丂乽從弌乿偲偼乽從揷乿偑曄壔偟偨傕偺偱丄偮傑傝惢墫偺墫傪從偔偨傔偺墫揷丄偺偪偵乽從乿偼乽敧栘乿偵側傝乽敧栘乿偲偄偆帤偑慻傒崌傢偝偭偰乽暷乿偵側傝丄乽暷揷乿偑乽暷捗乿偲偄偆偙偲偵側偭偨偲偄偆愢偑偁傝傑偡丅
丂乽摗曽乿傕傕偪傠傫乽摗妰乿丅乽捗嫽乿偼偦偺傑傑捗偑嫽偭偨拞怱偱偁傞偲偄偆丅
丂偙傫側偙偲傕偄偵偟偊偺埨擹捗傪扵傞僸儞僩偵側傞傛偆偱偡丅
丂曌嫮夛偼丄擔杮嶰捗偵娭偡傞帒椏偺尋媶乿乮堫杮婭徍丒1995擭12寧乯偵偼偠傑傝丄乽捗巗杽憼暥壔嵿僙儞僞乕尒妛偲垻憜塝嶶嶔乿乽埨擹捗峘敪孈偵岦偗偰乿乮栚嶈栁榓乯乽拞悽偺捗乿乮捗巗暥壔壽丒姙幒峃岝乯乽拞悽偺峘挰嵞尰乿乮峀搰導棫楌巎攷暔娰丒嵅摗徍巏乯乽埳惃恄媨偲埨擹捗乿乮恄媨巌挕慗媨挷嵏幒丒敧敠廆宱乯側偳傪峴偭偰偒傑偟偨丅
丂偟偐偟側偑傜丄曌嫮夛傪廳偹傟偽廳偹傞傎偳丄幚嵺偵埨擹捗峘傪孈傝婲偙偟偰傒偨偄偲偄偆梸媮偼怺傑傞偽偐傝偱偡丅
丂偲偵偐偔孈偭偰傒傛偆偲尵偆偙偲偵側傝丄栚嶈嫵庼偺偮側偑傝偐傜丄峀搰戝妛偺妶抐憌挷嵏偺尃埿丄拞揷崅嫵庼偺巜摫偺壓丄1998擭3寧31擔丄乽捗偺儖乕僣傪扵傞夛乿偺夛堳偺曽偐傜採嫙偺偁偭偨擇偐強偱帋孈傪峴偄傑偟偨丅堦偮偼恾-1偺桍嶳堚愓偺搶偺仛報偺掆攽抧岓曗抧丄傕偆堦僇強偼丄乽攏抮乿偲屇偽傟傞幖抧懷丅
丂曽朄偼丄傑偢侾儊乕僩儖傎偳昞柺偺搚傪孈傝丄拞揷嫵庼偑奐敪偝傟偨僕僆僗儔僀僒乕偲偄偆憰抲傪巊偭偰偺傕偺偱丄乽僐乿偺帤宆偺挿偝係儊乕僩儖偺忯忬偺僗僥儞儗僗惢偺栴斅傪僶僀僽儖僴儞儅乕偱懪偪崬傒丄乽僐乿偺帤偺奐偄偨晹暘偵奧偲側傞傕偆堦枃偺栴斅傪懪偪崬傒丄抧憌傪曵偝偢偵堷偒敳偔偲偄偆傕偺丅
丂嵟弶偵峴傢傟偨仛報偺応強偱偼丄係儊乕僩儖傎偳偺偲偙傠偵崟偭傐偄揇憌偑偁傝丄偦偺忋偵拑怓偄栚偺慹偝偑堎側傞嵒偺憌偑係丄俆憌廳側偭偰偄傞丅
丂堦斣壓偺憌偼丄傕偲傕偲偺奀掙偺僿僪儘憌乮娨尦偝傟偨搚乯偱丄嵒偺憌偼偦偺忋偵棳擖偟偨愳嵒偺巁壔憌丅
丂揇憌偺晹暘偵彫偝偄栘曅偺傛偆側傕偺偑尒傜傟丄庢傝埻傫偩儖乕僣偺夛夛堳偺乽慏乿偲偄偆婜懸傪傛偦偵丄屇傃婑偣偨峫屆妛偺妛寍堳偺堦尵偼乽埊偐壗偐偺怉暔偠傖側偄偐側乧乿丅
丂偟偐偟戝偒側惉壥偼丄嵒憌偺拞偵偁偒傜偐偵抧恔偵傛傞偲尒傜傟傞塼壔忬尰徾偵傛偭偰偍偒傞暚嵒偺愓偑偁傝丄抧憌偺怺偝偐傜峕屗帪戙偺偳傟偐偺抧恔偲悇掕偝傟傞偲偺偙偲偱偡偑丄偙傟偼悽奅揑偵尒偰傕捒偟偄昗杮偩偦偆偱偡丅
丂偙偆偟偨尰抧偱偺帋孈傪廳偹丄抧憌傗堚暔偺挷嵏傪偡傞偙偲偵傛傝丄偐偭偰偺埨擹捗偺抧宍丄挰偺巔偑晜偐傃忋偑傝丄峘傕尒偊偰偔傞偲峫偊傑偡丅偑丄偄偐傫偣傫丄堦斒巗柉偺抍懱偑偙偺傛偆側挷嵏傪懕偗傞偙偲偼偐側傝偺崲擄偑偮偒傑偲偄傑偡丅孈傞応強丄恖偲旓梡丄敳偒庢偭偨抧憌偺暘愅丒専摙丒曐懚側偳偱偡丅
丂偟偐偟丄堦斣廳梫側妶摦偱偁傞偲偺妋怣傪怺偔偟傑偟偨丅
(僕僆僗儔僀僒乕偵傛傞帋孈挷嵏偺曬崘偼乽暿嶜丗捗偺傎傫亀埨擹捗暔岅亁偺儁乕僕偱徯夘偟偰偁傝傑偡乯
丂帋孈偺幚峴傪専摙偟偩偟偨崰偐傜丄巗柉抍懱扨懱偱偺妶摦偵偼尷奅偑偁傞傛偆偵姶偠丄捗巗偵懳偟偰嫤椡傪偍婅偄偡傞偙偲偵偟傑偟偨丅
丂戞堦偺傕偔傠傒偼丄帋孈偵岞嫟偺応強傪巊傢偣偰偄偨偩偗傞偙偲丄戞擇偵偼丄尋媶婡娭傗巗偺妛寍堳偺嫤椡傪偍婅偄偡傞偙偲丄弌棃傟偽梊嶼偲偟偰偍嬥偺柺偱傕僶僢僋傾僢僾偟偰偄偨偩偗側偄偐偲峫偊傑偟偨丅
丂岾偄側偙偲偵捗巗偲偟偰偼傕偭偲傆偔傜傑偟偰庴偗巭傔偰偄偨偩偒丄偐偭偰偺埨擹捗偲偄偆抧堟偲偟偰偲傜偊丄埨擹挰丄婐栰挰偲偲傕偵捗偺儖乕僣傪扵傞夛偲巐幰偵傛傞乽埨擹捗暔岅幚峴埾堳夛乿乮愝棫憤夛1998擭5寧15擔乯偺敪懌傪尒傞偙偲偑弌棃傑偟偨丅偙偺巐幰偺嫟捠偺擣幆偲偟偰丄
丂乽柧墳偺抧恔偐傜500擭傪愡栚偵丄嫿搚偺婲尮傗惉挿傪尒偮傔側偑傜丄埨擹捗偑堢傫偱偒偨楌巎傗暥壔傪嫟捠偺暥壔堚嶻偲偟偰擣幆偟丄暥壔偺挰偯偔傝偲偡偡傔偰偄偔偨傔丄崙丄導丄峀堟巗挰懞丄偦偟偰嶰廳戝妛偺嫤椡偺壓丄奺斒偵徛傞帠嬈傪揥奐偟偰偄偙偆乧乿偲偄偆傕偺偱偡丅
丂帠嬈偼俇寧26擔偺婰擮島墘夛乽奀偺摴丒棨偺摴丒暥壔偺摴乿傪旂愗傝偵巗柉島嵗丄僔儞億僕僂儉丄摿暿揥丄偝傜偵偼儖乕僣傪朘偹傞僶僗僣傾乕丄摨偠柧墳偺抧恔偵傛傝奀偲偮側偑偭偨昹柤屛偺乽奐屛500擭僼僃僗僥傿僶儖乿傊偺嶲壛丄導徚杊杊嵭壽庡嵜偺乽柧墳戝抧恔儊儌儕傾儖僇儞僼傽儗儞僗乿偵帄傞傑偱條乆側僀儀儞僩偑峴傢傟傑偟偨丅乽捗偺儖乕僣傪扵傞夛乿偲偟偰偼丄偙傟傜偺帠嬈傊偺愊嬌揑側壓摥偒偲嶲壛偺屇傃偐偗丄愭偺帋孈偵壛偊丄偝傜偵擇僇強偺乽抧憌敳偒庢傝挷嵏乿丄梴惗寬峃岞墍偱偺乽巗柉嶲壛偵傛傞堚愓偺敪孈懱尡夛乿乮1998擭7寧20擔乯傪幚巤偟傑偟偨丅乮暿嶜丗捗偺傎傫亀埨擹捗暔岅亁傪偛傜傫壓偝偄乯
丂乽捗偺儖乕僣傪扵傞夛乿偑埨擹捗偺峘傪扵偡偙偲傪嬶懱揑偵傔偞偟偰俁擭丅惓捈側姶憐傪尵偄傑偡偲丄偦偺巔偼傑偩傑偩尒偊偰偒偰偄側偄偲尵偆偙偲偱偡丅
丂妶摦傪宱尡偟偰姶偠偨偙偲偼丄墦偄偲偙傠偐傜偺儊僢僙乕僕偼嬌傔偰旝偐偵丄枾傗偐偵丄帹傪偠偭偲偡傑偟偰丄偼偠傔偰偦偺堦晹偑暦偙偊偰偔傞偲偄偆偙偲偱偡丅偦偙偐傜偼崻婥偲婥偺墦偔側傞傛偆側挿偄宲懕偺愊傒廳偹偑偁偭偰偙偦帠幚偑晜偐傃忋偑偭偰偔傞傛偆偵巚偄傑偟偨丅
丂埨擹捗峘偺嵞尰丄偮傑傝巹偨偪偺偛愭慶扵偟偼丄偄傑偦偺僾儘儘乕僌偑巒傑偭偨偽偐傝丄乽暔岅偼偙傟偐傜偩偭乿偲偄偆婥偑偟傑偡丅
丂偲偙傠偱丄巹偨偪偑乮巹偑丠乯乽捗傪扵偦偆乿偲巚偄棫偭偨偺偼丄堦偮偺巚偄偑偁傝傑偟偨丅
丂偪傚偭偲婥偳偭偨尵偄曽偱柺偼備偄偺偱偡偑丄乽変乆偼偳偙偐傜棃偨偺偐丄壗幰偐丄偳偙傊峴偙偆偲偟偰偄傞偺偐乿偲偄偆巚偄偱偡丅
丂巹偨偪偼偄傑丄尰栶偺僶僩儞儔儞僫乕偲偟偰憱偭偰偄傞偺偱偡偑丄偦偺僶僩儞偼扤偐傜庴偗庢偭偨傕偺側偺偐丄偦偺僶僩儞偲偼壗側偺偐丄扤偵偳傫側傆偆偵搉偦偆偲偟偰偄傞偺偐丄偲偄偆媈栤偱偡丅尰幚偵尒傞偙偲偺弌棃傞偺偼乽棃偟曽乿偺帠幚偟偐桳傝傑偣傫偑丄偦傟傪偟偭偐傝尒偮傔丄妋偐傔傞偙偲偵傛偭偰丄乽峴偔枛乿偑尒偊偰偔傞偺偱偼側偄偐偲偄偆巚偄偱偡丅
丂巹偨偪偺廧傓偐偭偰埨擹捗偲屇偽傟偨抧堟偵偍偄偰丄偄傑偩乽棃偟曽乿偑幚姶偲偟偰尒傞偙偲偑弌棃偢丄乽偙偙偼偳偙丠傢偨偟偼偩傟丠乿偲偄偆尰忬偺傛偆側婥偑偟偰側傜側偄偺偱偡丅
丂偝傑偞傑側嵜偟暔傪偡傞偲丄嶲壛偟偰壓偝傞曽偺悢丄偦偺擬怱側傑側偞偟偵埑搢偝傟傞傛偆側巚偄傪偄偨偟傑偡丅
丂乽傆傞偝偲傪朘偹傞椃偼丄怱偺朰傟暔傪扵偟偵婣傞椃乿偱偁傝丄偦偺偨傔偵偼丄朰傟暔傪尒偮偗傞偙偲偺弌棃傞応強丄傕偆彑庤偵柤慜傪晅偗偰傒傑偟偨丅亀埨擹捗楌巎攷暔娰亁丅埳惃榩惣娸拞墰晹偺乽棃偟曽乿偺尰偺暔岅偑尒偊傞応強偱偡丅
丂偱偡偑丄娞怱偺拞恎丄枹偩憑嵏搑拞偱偡丅椡傪偍戄偟壓偝偄丅
丂劅捗偺儖乕僣傪扵傞夛丗懞嶳晲媣丒婰乮乽偁偡偺嶰廳啗111崋丂1998丒廐婫強廂乯劅
|